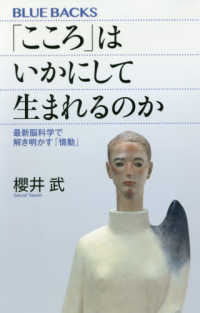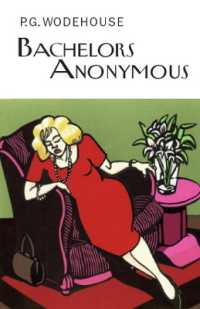内容説明
“普通”や“あたりまえ”を見直し、“わたし”が他者とつながる“ちから”を得るために、排除や差別とどのように向き合えばよいだろうか。差別‐被差別という二分法的見方を超えて、みずからの“差別する可能性”を認めたうえで、日常をより豊かに生きていくための重要な手がかりとして、排除や差別という営みや出来事を“活用”していこう。
目次
第1部 排除や差別を読み解くために(排除と差別の社会学を考える基本をめぐって;屠場をフィールドワークする;排除・差別問題における当事者とは誰か―「なぜこういうことに関心を?」という問いかけから;メディアから排除や差別を読む)
第2部 個別の問題を手がかりとして(ジェンダーは男/女の二項対立的概念ではない;同性愛への「寛容」をめぐって―新たな抑圧のかたち;異性愛主義のなかの女性の同性愛的欲望―それが確認されにくいのはどのようにしてか;「障害者」と「非障害者」を隔てるもの;ハンセン病差別の今日的様相 ほか)
著者等紹介
好井裕明[ヨシイヒロアキ]
筑波大学大学院人文社会科学研究科教授。1956生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
24
個として生きている我々。自分という存在と他者という存在との差異に気づいたときからどんな人間にも差別的な視点は生まれている。それを持つことをやめることは出来なくても、自らと異なる人間を、今の群れの中のマイノリティである人々の存在を、差異を認めながらも受け入れていくという考えというのは重要なのかもしれない。差別はいけませんという思考停止の言葉からは何も生まれない。それは誰の心の中でも起きているあたりまえの感覚なんだ。差異を認めた相手を迫害してはいけないという教育が必要なんだと思う。2016/11/25
Yuka
9
2009年に発行された本で、差別の構造は今も変わらないと思っていたけれど、内容は時代とともに変遷するのだなと実感した。 この本では屠殺場や部落などが取り上げられていて、LGBTQも項目はあるけれど比較的内容は軽め。新版の目次を見るとトピックから変えられているものも多くて、社会の変化とともに差別や排除の対象は移りゆくけれど、常に何かが排除されてしまうという社会の仕組みがあるのかなとも思った。 次は新版の方も読んでみたい。2025/07/06
タカナとダイアローグ
9
中古本。排除と差別について、様々なカテゴリー(屠場、メディアの責任、ジェンダー、障害、ハンセン病、ユニークフェイス、ひきこもり、新卒採用、外国人、部落)を考え始めるガイドブック。知らずにしてしまう差別と、知って知る差別の罪はどちらが深いだろうかと考えた。寛容という言葉が表す暗黙の上下関係(カミングアウトを受け入れる寛容さという、ほぼ暴力)について1番くらった。マジョリティ要素が多いからこそ、なんだか考えてしまう。?マイノリティ要素ももちろんあるけど)ひとりひとりが何だかんだ楽しく生きられる世の中にしたいな2023/11/02
木村すらいむ
4
2014年9月,全盲の生徒が通学途中に,白杖に躓いた人に蹴られたというニュースを見た.それに対するネットの反応は様々で,わからないことばかりだった.どう考えたら良いのか.本屋で偶然このタイトルを見かけ,手にとった.誰もが他者に影響を与えずには生きられないという前提から,差別的日常というテーマを導く.差別をする人とされる人がいるという二分法には,差別問題の属人化が含まれているといった話など,普通を問いなおすきっかけがつまっている.個人がよく考えること以外に,どんなことができるのかは示されていないのが残念.2014/09/20
ズマ
3
男女差別、障害者、同性愛者、外国人、部落差別など様々なトピックを設けて差別を論じた本。同性愛者はともかくレズビアンにまるごと一章用意されていたのがびっくりした。同性愛者の中でもレズビアンは「同性愛者差別」と「女性差別」の両方に抑圧されている。ビアンはメディアでも不可視化される。2012/02/10