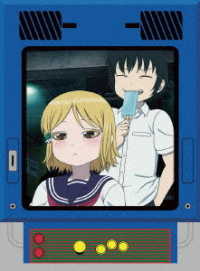出版社内容情報
労働法の基軸
内容説明
広く、深く、揺るぎなく。社会の変化をみつめ、労働法の変化とともにあった五十年。「菅野労働法学」が指し示す、労働法、労働法学のこれまでとこれから。
目次
第1章 ふるさとから東京へ
第2章 労働法学へ
第3章 菅野労働法学
第4章 労働政策への関わり
第5章 労働委員会での労使紛争処理
第6章 国際人として
第7章 大学人として
第8章 JILPTの調査研究に参加して
第9章 研究者生活を通じて
終章 労働法五十年の変化をみつめて
著者等紹介
菅野和夫[スゲノカズオ]
1943年東京都に生まれる。1966年東京大学法学部卒業。1968年司法修習修了。東京大学法学部助手・助教授・教授、中央労働委員会会長、労働政策研究・研修機構理事長を経て、東京大学名誉教授、日本学士院会員
岩村正彦[イワムラマサヒコ]
1956年生まれ。1979年東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、東北大学法学部助教授、東京大学大学院法学政治学研究科助教授・教授を経て、東京大学名誉教授、中央労働委員会会長
荒木尚志[アラキタカシ]
1959年生まれ。1983年東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、助教授を経て、東京大学大学院法学政治学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やまやま
11
菅野先生の一代記であり、「私の履歴書」であるが、自叙伝ではなく対談形式である。大学を出て労働訴訟専門の弁護士での就職を考えたが、学究の道を選ぶ転機があり、石川吉右衛門先生の後に東大で労働法を教えることとなる。労働法学界ではプロレーバーが当然であり、東大は労働者へのシンパシーがないので忌避するという雰囲気が変わって左右の融和が図られるようになったのはベルリンの壁の崩壊と期を一にしているようにも見えた。労使が保守的で中途半端な妥協しかできない時には政治主導もあるが、理論倒れの学者主導の改革は危険とする。2021/04/18
悠木
2
対談形式の「私の履歴書」であると同時に労働法史という趣。取りも直さず、菅野先生の歩みが労働法の歴史だからか。惜しむらくは、私自身が労働法の歴史の前提知識に欠けるので、本書の、菅野先生のすごさを十分受け止めきれなかったこと。学者も研究・教育だけでなく、大学事務、公職、国際活動と忙しそう。また、労働法の理解・背景知識が深まればもっと違う感想を持ちそうなので、いつの日か再読したい。2024/09/16
はび
1
日本労働法学の大家である著者の一代記。法曹関係者であれば、菅野先生の「労働法」を知らない者はいないであろうが、このような地位を築き上げるまでの菅野先生の人生が、氏の二人の弟子(荒木先生、岩村先生)との対談形式によって描かれる。労働法学という学問が、我々が逃れられない労働という日々の営為と密接に関係するからこその隆盛を極めていることも幸いしたかもしれないが、そうは言っても菅野先生がこれほどまでの地位を築いたのは、暖かそうなお人柄と常に日本の労働学の転換点を感じ取って研究を積み重ねてきた結果なのだろうと思う。2022/07/26