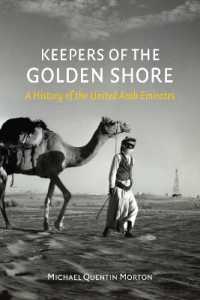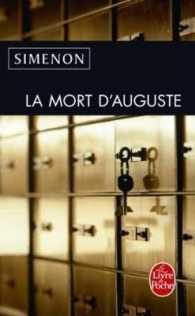出版社内容情報
さまざまな社会問題とも密接にかかわる民法総則・物権法領域のスタンダード・テキスト。2021(令和3)年の民法等の改正をふまえ,主に共有に関する事柄を中心に記述を改めたほか,その他の法制や社会の変化をにらみ解説の見直しを行った。信頼の第8版。
内容説明
民法は、試験科目としてだけでなく、自分の周りや社会のあり方を考える上での“大切な武器”になる。社会生活を送る上で不可欠の存在である民法をわかりやすく、かつおもしろく解説する。
目次
1 基礎(第一のキーワード―人;第二のキーワード―所有権;第三のキーワード―契約)
2 展開(法人;担保物権;代理―そして法律行為を学ぶ;時効)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
お抹茶
2
読んだのは第7版。法学部生以外でも読めるレベルで,オーソドックスな構成だと思う。法律系資格を目指す人のおさらいとしてもよい。ややこしい物権変動とか代理や時効,善意無過失という独特な用語も理解できる。契約解除では,一般的に催告をして相当期間内に履行がないときに解除の意思表示を求められ,消費者の不作為をもって申し込みや承諾の意思表示をしたものとみなす条項や法外な違約金を課す契約は無効。不実の登記がされている土地を譲渡された者は誰に対抗できるかなど,論点整理にも役立つ。2021/10/14
dokulogue1
1
図書館本。民法の基礎的なところを確認したいと思い読んだ。レベルとしてはベーシックであり、読みやすいものだった。専門的に学ぶには物足りないだろうが、私としてはギリギリ読み切れる難しさだったと思っている。最新情報に対応しているのもうれしい。2022/08/21
たまぞう
0
民法学習の中心は人、所有権、契約という3つの要素にある、という基本的な視点はわかりやすくて良かった。ただし、要件・効果、第三者への対抗といった基礎概念の説明はないので、まったくの未習者が1冊目に読むと難しいかも。また、著者は不動産登記法の専門家だけあって、不動産登記や動産譲渡登記、抵当権などの解説が詳しく、初学者の自分には難しかった。それにしても、不動産の二重譲渡が論理的には出来てしまうことはどう考えても法律の欠陥(主たる原因は民法176条)としか思えないけど、学習が進めば納得できるようになるのだろうか。2025/03/01
-

- DVD
- COMBAT! BATTLE26