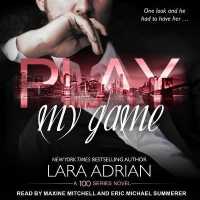出版社内容情報
稲沢 公一[イナザワ コウイチ]
著・文・その他
内容説明
苦しみをかかえて逃げることのできない人を前にしたとき、私たちには何ができるのか?援助を構成する要素や援助モデル、理論史の解説などをとおして、人が人を助ける理由にあらためて立ち返る、新たな援助論。
目次
援助を構成する3要素
援助の「必要条件」
何が援助の対象なのか―援助対象を把握する視点の変遷
「援助対象」を構成するもの―援助対象を把握する枠組み
4つの援助モデル
他なる人
援助関係の4性質
援助関係論はどのように発展してきたか―ソーシャルワークの理論史
援助過程がめざすところ
「人と人との」関係性
「無力」であること
なぜ、人は人を助けるのか
著者等紹介
稲沢公一[イナザワコウイチ]
1960年、京都生まれ。1997年、東洋大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士後期課程修了。現在、東洋大学ライフデザイン学部教授。専攻:理論福祉学、精神保健福祉論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
31
対人援助職の援助するとはどういうことかを考察した内容です。まず共感できたのは、援助とは人と人との関係性も問題であり、たとえ何もできなかったとしてもその傍らに居続けることの大切さを述べられていたことは非常に重要だと思いました。僕は傍らに居続けることの重要性を福祉労働のなかでしっかりと理論化したいと考えています。少し疑問点としてあったのはナラティブアプローチに対する見方です。語りを重要視する必要性はわかるのですが、語りで真実は作れません。語りの背景にある客観的事実をみる柔軟な目が必要なのだと思ったりしました。2018/01/25
アナクマ
30
4章5章。援助の対象は4象限で考えよう(個人・環境・物語・文化)。すなわち、個人or環境、主観or客観の切り口で整理するのだが、包括的な視点を忘れてはいけない。◉個人:改善が見込めない場合もある。◉環境:対象者を傷つけることはないが、周囲の調整が必要。◉物語(ナラティブ):エピソードをプロット(筋)で結び、緩い因果関係で説明するもの。援助者はあくまで教えてもらう立場であり主導権は少ないが「書き換え」を期待する。◉文化:世間に流通している価値観だが、差別・偏見とも言える。変容にはとても時間がかかる。→2020/02/24
Hammer.w
23
教科書でありながら自己啓発本にもなります。覚えたいというより、ピンときた文章にしおりを貼っていきました。p.49援助対応の4側面。同時に包括に視点を求められる。p.63くれぐれも専門的な用語や知識で知ったかぶりをしない。文化モデルとは、偏見や差別の解消を直接めざす活動。p.78ステレオタイプ。p.119ストレングスモデル。地域生活の支援。p.146コップ半分の水。p.167ゴール目標とはこの1〜2週間のあいだに実現できる行動プラン。p.180「変えられるもの」は変えていかなければなりません。2023/03/01
saiikitogohu
4
「他なる人をあたかも私の分身であるかのように、理解し尽くしているかのように取り扱うこと、それこそが、他なる人の尊厳を踏みにじる行い」「人間の尊厳とは、すべての人が、自分のみが知りうる何か、他の人の理解や推測を越え出る何かを保持していることなのである」(p77) この人のことは自分が一番よく分かっている、だとか、この人にはこのように対応してれば間違いない、だとか。「他人を助ける」という営みには「他人を知り尽くしている」という傲慢さが常につきまとう。「分からない」けど、「ただ傍に居る」ということの難しさ。2017/09/16
-

- 電子書籍
- 狂人パパができちゃいました【タテヨミ】…