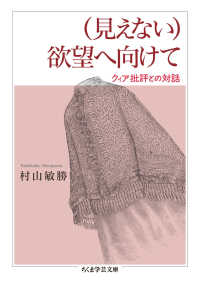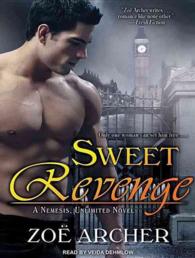出版社内容情報
困窮や孤立,今日的なニーズへの支援として「伴走型支援」への期待が高まっている。この支援を通して社会はどのように変わるのか。10名のパイオニアが実践や研究の中から紡ぎ出す貴重なメッセージから,その概念や方法,課題や可能性について多面的に考える。
内容説明
ひきこもり、8050問題、ゴミ屋敷、生活困窮、子どもの貧困…。“深まる社会的孤立”につながり続ける支援を!
目次
第1部 伴走型支援を考える(伴走型支援の理念と価値;なぜ伴走型支援が求められているのか;単身化する社会と社会的孤立に対する伴走型支援)
第2部 人と地域に伴走する支援(伴走型支援と地域づくり―住民とともにつくる伴走型支援;アウトリーチと伴走型支援;越境する伴走型支援;日本における伴走型支援の展開)
第3部 新しい社会を構想する(伴走型支援と当事者研究;伴走型支援は本当に有効か;伴走型支援がつくる未来;あらためて伴走型支援とは何か)
著者等紹介
奥田知志[オクダトモシ]
NPO法人抱樸理事長、東八幡キリスト教会牧師。これまでに3600人(2021年3月現在)以上のホームレスの人々の自立を支援。その他、生活困窮者自立支援全国ネットワーク共同代表、共生地域創造財団代表理事、全国居住支援法人協議会共同代表、国の審議会等の役職も歴任
原田正樹[ハラダマサキ]
日本福祉大学社会福祉学部教授。専攻は地域福祉、福祉教育。日本地域福祉学会会長、日本福祉教育・ボランティア学習学会会長などを務める。厚生労働省の地域力強化検討会(座長)、地域共生社会推進検討会などに参画。全国生活困窮者自立支援ネットワーク理事、全国社会福祉協議会・ボランティア市民活動振興センター運営委員などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
ちえ
Michio Arai
Yuko
gami
-
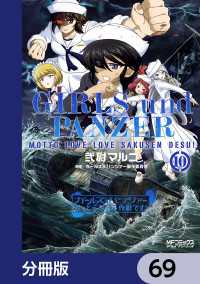
- 電子書籍
- ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作…