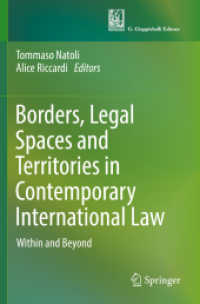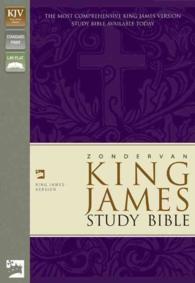内容説明
私たちは本当に自分自身を正しく認識しているだろうか。記憶や感覚、思考といった人間の認識のしくみとその「不思議さ」に迫る認知心理学。基礎から発展の歴史まで、必要な知識をコンパクトに網羅。知識詰め込み型ではなく、WORK、EXERCISE等、考えながら体感しながら学べる工夫が満載の入門テキストです。
目次
1 「誤り」から見る認知心理学
2 感じる―感覚
3 捉える―知覚
4 覚える―記憶の基礎
5 忘れる―記憶の展開
6 わかる―知識の成り立ち
7 考える―問題解決と推論
8 決める―判断と意思決定
9 気づかない―潜在認知
10 認知心理学の歩み
著者等紹介
服部雅史[ハットリマサシ]
立命館大学文学部教授。2016年4月より:立命館大学総合心理学部教授
小島治幸[コジマハルユキ]
金沢大学人間科学系教授
北神慎司[キタガミシンジ]
名古屋大学大学院環境学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きゅー
8
認知心理学と言われてもあまりピンとこないが、内容としては人間の認知(対象を知覚した上で判断する過程)がいかにあやふやなものであるかを様々な例証を用いて説明する一冊となっている。モノを見た瞬間から始まり、何かを決定するまでに私たちは様々なバイアスのもとで判断を下す。あるいはその判断は、モノを見る前から確定している場合もある。認知心理学という学問を知るため、というよりも自身の行動を省みるための一冊にうってつけ。参考図書も掲載されているので、ここから広げることができる。2023/06/14
みかん。
8
認知心理学と隣接する社会心理学の関係は良好であり、また工学や医療などにも認知心理学は広がりつつある。認知心理学はまた心理学における折衝役を兼ねている。過去の内観を中心とした意識心理学は認知心理学の台頭ののち、心理学における折衝役の役割を完全に失墜したといえる。2023/01/29
himawari
7
認知心理学の基礎的な知識を、簡単に説明してくれている。認知心理学専攻以外の学生にも興味を持ってもらえるように書かれているということで、専門的過ぎず、どれも興味深くて面白い。こんなにも人間の認知機能は不確かなのかと驚く。人間の知覚能力はカメラなどの機械とは違って、見たままを認識しているわけではないのだな。スキーマ、閾値、錯覚や錯視など、知っているものもあったが、分かりやすく解説されていたので理解が深まり、楽しく読めた。2016/11/02
aiken
6
2015年の本。ほんとに基礎から学べた。知ってる話も多く復習になった。そこそこ新しい本なので現在の学問とのつながりもわかり助かった。印象に残ったのは、論理と合理は異なるということ。流行りのGPTによれば、論理は証拠や論拠を厳密に分析し矛盾がないように考え、合理は、加えて個人の目標、価値観、ニーズ、状況、経験、感情に基づいて、判断を下すらしい。何を問うかを本で学び、答えをGPTで学ぶ。現代は、このような振る舞いを「学びて時にこれを習う」といったりするもかもしれない。いや、いわないか。2023/04/04
mkt
5
記憶は思っている以上に不正確/何かを知ると知らない状態を想像するのは難しい/知識は見方を変えるのを難しくする/感じるのは、感覚と感情の2つがある/知覚分類①何②どこ/感覚貯蔵といわれる感覚情報の保持機能がある/記憶は失ったり、歪んだりする/メタ認知は不正確なことが多い/問題の解決はヒューリスティックが用いられることが多い/効用は意思決定の重要な要因で金銭的価値とは一致しない/基準の違いによって選択は変わる/理由が思い付きやすい選択肢は選ばれやすい/意識は後から/ 20220514読了 232P 18分 2022/05/14