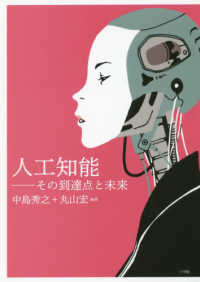内容説明
「互いにわかりあうのがよいコミュニケーションである」という思いに囚われている現代社会。本書はその常識に疑問を投げかけ、コミュニケーションの文化的豊かさを、リアルな人間模様を描く事例から描き出し、新しい社会学を提示します。
目次
第1部 コミュニケーションの社会学とはなにか(コミュニケーションと社会学;Aくんへのレッスン(1)対話と遊戯としてのコミュニケーション
Aくんへのレッスン(2)パラドックスと接続としてのコミュニケーション
単独性とコミュニケーション)
第2部 コミュニケーションの社会学になにができるか(対話としてのコミュニケーション;遊戯としてのコミュニケーション;非対称のコミュニケーション;フラット化するコミュニケーション)
著者等紹介
長谷正人[ハセマサト]
早稲田大学文学学術院教授
奥村隆[オクムラタカシ]
立教大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
aiken
7
2009年の本。図書館本。コミュニケーション能力が必要と当たり前に言われる昨今だが、本当にそうなのかと疑い読んでみた。読んだ理由は、前提を疑い脱構築する現代思想の哲学入門本を読んだからかもしれない。結果、たいへん参考になった。コミュニケーションにも種類があり、イジメや暴力もコミュニケーションの一部であると捉えた時、そういったコミュニケーション能力が活性化してしまうと、フラットという名の基に、いびつな閉じた世界が生まれる。現在のSNS社会や学校社会はまさにそれらしい。それを救うのは、孤高の哲学だけなのかも。2022/10/07
coaf
6
読み物として純粋に面白かった。当たり前のことを分析することの面白さと難しさを実感した。新たな視座を獲得した。文献探しの役に立った。2012/08/24
multi_b
3
コミュニケーションの”常識”を解きほぐしていく本。現代で”良い”とされるコミュニケーションは歴史を振り返るとそうではなかった。 社会心理学の書籍と合わせて読むと理解が深まると思います。2016/10/22
笹の葉sarasara
3
コミュニケーションの3つの側面。(本書を軽く参考に)A.平等な対話、討議による了解、合意志向的な性格B.貨幣、役割を媒介とする市場、機能的な性格C.共有経験の蓄積に基づくその関係に固有な性格。近年、AがCの領域にも浸透してきたことがコミュニケーションの閉塞感を生み出しており、完全な相互了解を志向する「コミュニケーションの神話」からの自由を示唆する本書の記述は特におもしろい。言葉の射程は驚くほど短い、にもかかわらず言葉の力を過信してしまいがちな私にとってこの本は特に意義があったと思う。2010/01/02
子音はC 母音はA
2
「社会と個人」の間を補完するものとしてコミュニケーションにまつわる社会学的思考に因った方法論を提示し、さらにはそれらを下敷きにし様々な事象を扱う。(アイドルとファンの関係)など、特に関係性が対等ではない(非対称コミュニケーション)に重きを置いて纏められている。2014/07/17
-
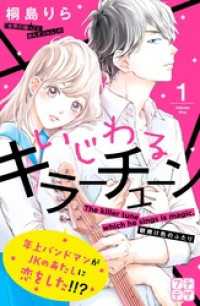
- 電子書籍
- いじわるキラーチューン プチデザ(1)
-

- 電子書籍
- 霊魂や脳科学から解明する 人はなぜ「死…