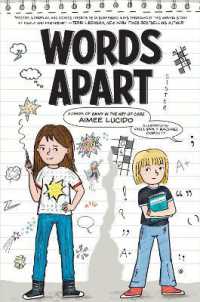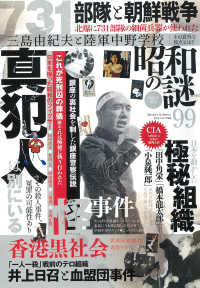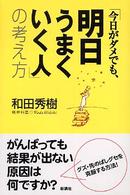内容説明
日常生活ではあまり意識されることのない「地域」。しかし、そこでは数多くの社会関係が取り結ばれている。現代日本の地域生活の分析と地域研究の歴史の再考から地域とそこでの生活の問題と意味を考える。
目次
第1部 地域を考える(“地域”へのアプローチ;地域社会とは何だろう;地域を枠づける制度と組織;地域に生きる集団とネットワーク;地域が歴史を創り出す 歴史が地域を創り出す;なぜ地域が大切か)
第2部 地域を見る(子育てと地域社会;学校と地域;自営業者たちと地域社会;高齢化と地域社会;エスニック集団と地域社会;地域社会の未来)
著者等紹介
森岡清志[モリオカキヨシ]
現職、首都大学東京大学院人文科学研究科教授、世田谷自治政策研究所所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
- 洋書
- Words Apart