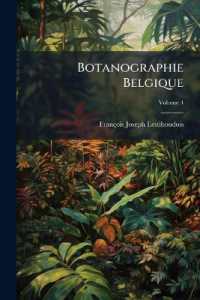出版社内容情報
刻一刻と変動し,複雑でとらえにくい国際金融の姿を懇切丁寧にわかりやすく解説する入門テキスト。豊富な実務経験をもとに,為替・理論・制度のシステムを具体的・総合的に説く。新版化にあたり,情勢変化や制度変更を全面的に踏まえて改訂し,ITとの関わりも詳述。
《主な目次》
第1章 外国為替のしくみと形態
第2章 外国為替相場
第3章 外国為替市場
第4章 為替リスクヘッジの手段と方法
第5章 国際収支のしくみ
第6章 為替相場と国際収支
第7章 為替相場の決定理論
第8章 国際通貨制度のしくみ
第9章 国際通貨制度の変遷
第10章 ヨーロッパの通貨統合
第11章 国際通貨制度の課題と制度改革への道のり
第12章 円の国際化
終 章 IT革命と国際金融
内容説明
刻一刻と変動し、複雑で捉えにくい国際金融のすがたを丁寧かつコンパクトに解説し、「為替」「理論」「制度」という構成に従って具体的・総合的に説いた、定評ある入門テキスト。ユーロ誕生など新たな動向や制度面の変化、ITによる影響などを全面的に取り入れ、新版化。
目次
外国為替のしくみと形態―貿易決済や資金移動の具体的なしくみ
外国為替相場―銀行が建値する為替相場の種類と性格
外国為替市場―グローバル・マーケットに成長した為替市場
為替リスクヘッジの手段と方法―次々と開発される新しい金融取引
国際収支のしくみ―対外経済取引の統計の作成方法
為替相場と国際収支―相場変動はどのような影響を与えるか
為替相場の決定理論―為替相場理論はどのように変わってきたか
国際通貨制度のしくみ―円滑な決済を可能とする制度的枠組み
国際通貨制度の変遷―どのような歴史を経て今日の姿になったか
ヨーロッパの通貨統合―単一通貨の実現をめざした歴史的大事業
国際通貨制度の課題と制度改革への道のり―現在の国際通貨制度の問題点と解決策
円の国際化
IT革命と国際金融
著者等紹介
秦忠夫[ハタタダオ]
1940年島根県生まれ。1963年に京都大学経済学部を卒業し、東京銀行に就職、95年3月までおよそ30年間同行で勤務しました。この間、大部分を東京、ニューヨーク、パリ、でエコノミストとして、おもに世界経済や国際金融・通貨問題の調査と報告の仕事に従事してきました。いってみれば、典型的な国際金融バンク・エコノミストとしてのキャリアを積みました。1995年4月から、愛知淑徳大学に新設された現代社会学部で、「国際金融論」「演習」などを担当することになりました。現在は、大学院の現代社会研究科で「国際経済システム論」なども担当しています。現在は主として、国際金融の制度面の問題について研究しています
本田敬吉[ホンダケイキチ]
1936年神戸市生まれ。1959年東京大学法学部卒業後、東京銀行入行。米国ピッツバーグ・メロン銀行でエコノミスト研修のあと、東京銀行のニューヨーク、シンガポール、東京などでの銀行業務のほか、アジア民間投資会社、イラン日本国際銀行、カリフォルニア・ファースト(現ユニオン)銀行、シカゴ東京銀行などでも国際投融資業務で色々苦しいことや、感激することなどを経験しました。すこし歳をとってからは、国際投融資の審査役、取締役調査部長、東銀系シンクタンクの社長などを歴任。この間、国際商業銀行エコノミスト会議幹事、OECD民間諮問委員会の経済政策委員会副委員長、先物業協会日本支部長、ブレトンウッズ改革委員会日本事務局長、米国ビジネスエコノミスト会議員、市場開放苦情処理専門委員、京都大学と上智大学講師なども兼務してきました。1996年4月からサン・マイクロシステムズ株式会社会長に就任し、情報処理革命の時代に挑戦し、eコマースやeバンキングも研究してまいりました。かたわら東京三菱銀行出資の財団法人、国際通貨研究所の評議員も引きうけ、国際金融・通貨制度問題の研究にも取り組んでいます
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
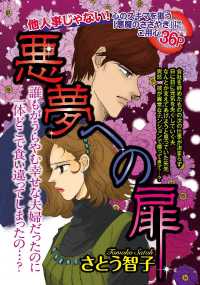
- 電子書籍
- 悪夢への扉 - 本編 ご近所の悪いうわ…