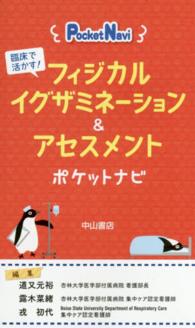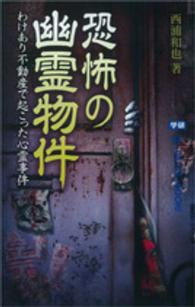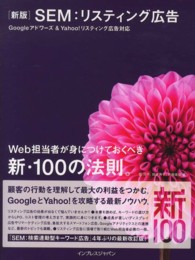出版社内容情報
日本人はどのように塩を作り、塩と関わってきたのか。
製塩のための設備や用具、製塩技法、塩にまつわる言葉の数々。さらには製塩業の経営や塩の流通と消費など、塩と日本人のつきあいを様々な視点から浮かび上がらせる名著、好評の【第四版】
【目次】
古 代
藻塩―製塩に海藻をどう使ったか
堅塩―はたして貧者の塩であったのか
塩山―権門・寺社は山林を占有して塩をえた
塩尻―略奪的製塩法
塩浜―塩浜は何時どのようにしてできたか
塩ごし―鹹砂の塩分をどのように溶出したか
塩談1 塩で見付かった平家の落人
煎熬塩鉄釜―土器による焼塩から鉄釜による焼塩へ
投木―なげきこりつむとは―薪の山
汲潮浜―平安時代の揚浜系塩田の発掘調査
古代の塩生産で著名なところは
古代において塩はどのように流通し消費されたか
塩談2 潮汲車
中 世
中世の塩浜と塩生産者の実態はどうであったか
瀬戸内の何処で塩が作られたか
塩の荘園弓削島―汲潮浜
若狭湾岸の製塩―自然揚浜
塩談3 恩を売って塩を売る
伊勢神宮の塩浜―古式入浜の出現
南伊勢の竈方集落の製塩
塩焼の物語『文正草紙』
塩釜神社の御釜は煎塩鉄釜か
『兵庫北関入船納帳』にみられる塩
塩談4 ルイス・フロイスのみた塩釜
京都の塩は何処からどう入ったか
興福寺の塩座―中世の塩流通機構
戦国大名はどのような塩政策を行なったか
安土築城ころから塩価が安くなる
近 世
近世にはすべての製塩法が出揃う
三陸海岸では海水を直接煮つめた
南九州や南西諸島には中世以前の方法が残っていた
日本海岸では自然揚浜法が一般的であった
太平洋岸の海湾内では古式入浜法が行なわれた
能登では岩石浜に塗浜(置浜)を作った
塩談5 鯛の浜むし
東北では山奥でも塩を作った
製塩にはどのような鉄釜が用いられたか
鉄釜以外の塩釜にどのような釜があったか
塩談6 山窩の塩凝
入浜塩田は何時・何処でできたか
入浜塩田はどのように干拓・造成されたか
瀬戸内十州塩田はどのように発展したか
入浜塩田ではどのような作業が行なわれたか
入浜塩田は賃銀労働を使った
塩談7 元禄赤穂事件と塩
松葉焚石釜による煎熬
石炭を最初に使った産業は製塩業である
入浜塩田の経営はどのくらいもうかったか
入浜塩田の地主・小作制はどのように展開したか
塩田地主と小作の性格
備前野崎塩田の当作歩方制
塩談8 盛り塩と撤き塩
入浜塩田一〇〇町歩地主の経営
瀬戸内十州塩はどこへ移出されたか
赤穂から見た大坂の塩市場
江戸下り塩問屋の取引慣習
塩談9 塩の値段
江戸行きの塩船はどれほど利益をあげたか
瀬戸内塩業は近世に操短(休浜)同盟を結んでいた
操短同盟(休浜)の理論書『塩製秘録』
諸藩の塩専売(国産仕法)
江戸湾に塩田二千町歩の干拓を夢みた男
内容説明
日本の伝統的塩作りのすべて!!!
目次
01 古代(藻塩―製塩に海藻をどう使ったか;堅塩―はたして貧者の塩であったのか ほか)
02 中世(中世の塩浜と塩生産者の実態はどうであったか;瀬戸内の何処で塩が作られたか ほか)
03 近世(近世にはすべての製塩法が出揃う;三陸海岸では海水を直接煮つめた ほか)
04 近代(明治維新は塩業にどのような影響を与えたか;塩田の地租改正は田畑の場合とどう違ったか ほか)
著者等紹介
廣山尭道[ヒロヤマギョウドウ]
1925年兵庫県赤穂市に生まれる。大正大学国文学科卒業。日本歴史学会・日本塩業研究会会員。市立赤穂歴史博物館館長を務めた。2006年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
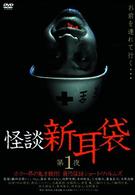
- DVD
- 怪談新耳袋 第1夜