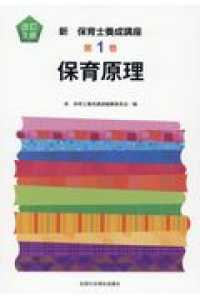内容説明
人に化け、人と交わり、人に憑き、ときに人を悪辣に騙す。その妖しい怪異談の数々を紹介。物の怪として恐れられたり、稲荷神として神格化されたり、謎多い日本人の「きつね観」を探究した名著が復刊!!
目次
第1章 化ける狐
第2章 日本での狐の名
第3章 狐、人と交わる
第4章 化け狐
第5章 狐は仇をする
第6章 狐の報恩と贖罪
第7章 狐の玉・狐火・狐の嫁入り
第8章 狐憑き
第9章 狐と稲荷
第10章 荼吉尼天
著者等紹介
笹間良彦[ササマヨシヒコ]
大正5年(1916)東京に生まれる。文学博士。日本甲冑武具歴史研究会会長を務め、数多くの編著書がある。平成17年(2005)11月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
13
甲冑の専門家として数々の著作もある高名な在野の研究者による本。我が国の民間信仰に根を張った狐の祟り等について、主に江戸期の随筆類から採話する。話題は動物婚から変化、仇討や報恩の様々から、インド南方の土俗神ダキニがヒンズーに包摂され、更に仏教を経てシナで大きく変容、特に妖狐との混淆の歴史を述べる。江戸期に知識人さえヘンゲする狐を信ずる点を奇異に述べつつ、列挙に務める。多少分析的記述はあるが体系的ではない。私が新聞を読み始めた頃には狐憑きとされての暴行死が屡々報じられた。最近は絶えたが、狐と稲荷の混同は尚残る2024/10/12
福ノ杜きつね
2
古文書や古典文学作品を中心に、日本人がキツネについて抱いてきたイメージを深掘りした大著。人との間に子をなし、悪戯で人を困らせるかと思えば、人に恩を返す義理堅さも見える。時に禍を呼ぶ妖となり、人を護る神の使いにもなる。一民族の間で、これほどに多様な姿で捉えられる生き物は、考えてみれば特異な存在だ。まさに、化ける動物としての本領発揮。キツネ化かされる話が迷信だなんてとんでもない、と言いたくなる。でなければ、ここまで多様な伝承が語られ続けるはずがないではないか。2024/05/18
-

- 電子書籍
- 見えなくても聞こえなくても愛してる【タ…
-
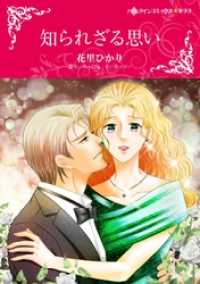
- 電子書籍
- 知られざる思い【分冊】 12巻 ハーレ…