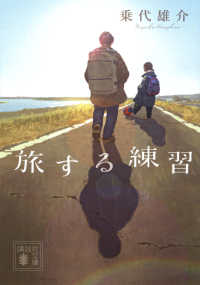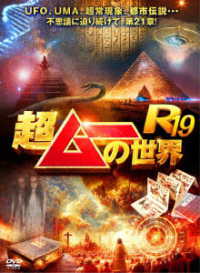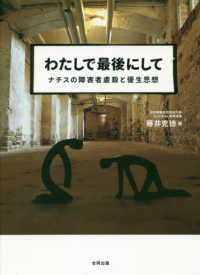内容説明
入れ墨文様から文字へ。宗教儀礼や呪術としての入れ墨の、刑罰としての入れ墨への変化。そのような入れ墨の文様と甲骨文字の関係、甲骨文字から漢字への変遷。文様や文字の持つ意味が、人間の中でどのように変化していったのかを、墨家集団の成立からその思想の墨子への昇華を軸に、探求していく。
目次
第1章 文字論の宇宙
第2章 古代中国とヨーロッパに於ける供犠、呪術としての刑罰の対照
第3章 殷文化と少数民族に残る習俗
第4章 殉葬論
第5章 書の民俗学
第6章 思想の基底となる階層と宗教
第7章 墨子新原論と賞罰
第8章 兼愛論の源泉
第9章 書の基底をなす宗教性
著者等紹介
松宮貴之[マツミヤタカユキ]
1971年滋賀県生まれ。東京学芸大学芸術課程書道専攻卒業。二松學舍大学文学部修士課程中国学専攻修了のち中国北方交通大学(現在の北京交通大学)語学に留学。その後、立正大学文学部博士課程国文学専攻、満期退学。総合研究大学院大学より博士(学術)の学位取得。現在は佛教大学文学部非常勤講師(書論・書道実技・日中書道史担当)、四国大学大学院非常勤講師、西安培華学院客員教授、国際日本文化研究センター共同研究員、立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員。専門は書論、日中文化交流史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
5
漢字の起源を入れ墨の紋様に求め、入れ墨あるいは殷文化と墨家の思想との関係、書の宗教性へと話が及んでいくが、入れ墨と文字の起源の雑感という感じで議論としてあまりまとまりがない。論証というか個別の事項について説明が不足している点も多々ある。2021/09/02
とりもり
0
著者は書家とのことで、学術的な裏付けは必ずしもないことを後書きで知る。漢字の起源を入れ墨(☓や十)に求め、そこから漢字の発展を語る内容は面白いが、ちょっと牽強付会な感じがする。墨家を巡る考察が一番興味深く、墨子の思想についてはあまり知らないので面白かった。墨刑をされた奴隷的立場から思想を高めたので、博愛主義を語っているという考察は興味深いが、墨家自体の由来に諸説あるようなので、これもあくまで推測。全体にどこまで信じていいのやらという点で微妙な一冊。★★★☆☆2021/10/21