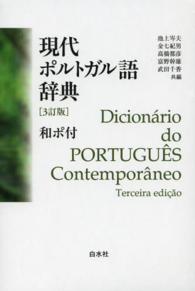内容説明
動物文明(畑作牧畜文明)と植物文明(稲作漁撈文明)の対立の中で文明史を再考察する。稲作漁撈文明の価値の再発見が地球環境の保全につながる。
目次
第1部 稲作漁撈文明の起源と展開(森と米の文明を求めて;稲作農耕の起源;長江文明の発見;四二〇〇年前の気候変動と東アジアの民族移動)
第2部 畑作牧畜文明の起源と発展(黄河文明は畑作牧畜文明だった;麦作農耕の起源;家畜の民の拡散と世界支配;大河のほとりの乾燥化と畑作牧畜文明の誕生;オリーブ栽培の起源と発展)
第3部 日本はなぜ農耕革命を欠如したのか(農耕牧畜がなくても先進地域だった日本;なぜ稲作は広まらなかったのか;日本文明史のなかの弥生時代)
第4部 稲作漁撈文明の人類史的意味(稲作漁撈文明が地球と人類を救う)
著者等紹介
安田喜憲[ヤスダヨシノリ]
1946年三重県生れ。東北大学大学院理学研究科修了、理学博士。広島大学総合科学部助手、京都大学大学院理学研究科教授(併任)、フンボルト大学客員教授、国際日本文化研究センター教授などを歴任。現在、東北大学大学院環境科学研究科教授、スウェーデン王立科学アカデミー会員。環境考古学の確立で紫綬褒章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
井上岳一
1
気候変動が人類にどのように影響を与えてきたのかということを知るには良い本。特に、農耕の誕生は寒冷化が契機になっていることを、花粉調査の結果をもとに明らかにしている点は評価。しかし、後半の哲学論がいただけない。縄文時代や江戸時代を理想視し過ぎ。あと、既存の学界に対する恨み節が随所に垣間見えてそれも辛い。ルサンチマンの人なんだな。せっかく良い研究しているんだから、もっと自由に解き放たれたら、偏見もなくなって、もっと良い研究成果を残せるようになると思うのだが。2016/07/02
ハイパー毛玉クリエイター⊿
1
“畑作牧畜文明ではなく、稲作漁撈文明こそが、これから50年ほどの間に訪れることが予測されるエネルギーシステムの崩壊後の世界を救うのよ”という著者の見解のもと展開される、考古学と文化人類学の中間のようなこの1冊。面白いが専門的なので読むのに時間がかかった。あと稲作漁撈文明とやらが本当にそんなにも人と地球にやさしい生き方だったのか? 理想化しているだけでは? と、あまり現実味を以て想像することができなかった。しかし、エネルギー枯渇後の人類の生き方を考えることは、我々の世代にとっては必須の課題であることは確か。2015/09/17
-
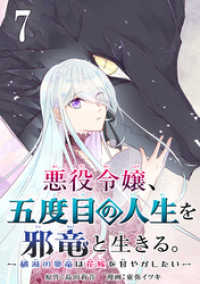
- 電子書籍
- 悪役令嬢、五度目の人生を邪竜と生きる。…