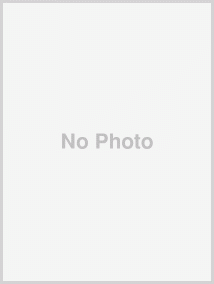出版社内容情報
信仰の有無にかかわらず日本人全体が寺院の檀家として位置づけられた中での仏教の変質過程を検討する。 目次 幕藩体制と仏教 日蓮宗不受不施派初期の動き 西中国地方における真宗的特質の展開 幕府の都市寺院支配 寺院の庶民定着と伝法 近世五山派教団【ほか】
内容説明
近世仏教の展開と民衆化への過程を捉える。仏教が本当の意味で民衆一人一人の信仰として定着したのは、なんといっても江戸時代である。本書は、幕藩体制確立期の仏教諸宗派と世俗権力の確執や民衆の信仰形態など、近世仏教の諸相を様々な視角から検討し明らかにする。
目次
1 幕藩体制と仏教―キリシタン弾圧と檀家制度の展開(寛永期のキリシタン弾圧と島原の乱;類属戸籍帳の作成と檀家制度の確立)
2 江戸時代における仏教の展開(日蓮宗不受不施派初期の動き;英彦山修験(山伏)と信仰圏の実態
諸山諸社参詣先達職をめぐる山伏と社家―吉田家の諸国社家支配化への序章
近世九州における日蓮教団の展開―いわゆる大村法難を中心に
近世初期仏教思想史における心性論―雪窓宗崔『禅教統論』をめぐって
幕府の都市寺院支配―近世堺を中心に
近世真宗遺跡巡拝の性格
近世の浄土宗念仏者雲説と七日別行百万遍
西中国地方における真宗的特質についての考察
近世五山派教団―天明・寛政寺院本末帳を中心にして
遊行五十六代傾心上人の岡山廻国
寺院の庶民定着と伝法―浄土宗寺院を中心として
松前藩における近世仏教)