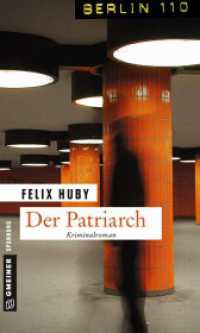内容説明
「運命」はなぜハ短調で扉を叩くのか?クラシックの長調、短調にはワケがある。現役作曲家が解き明かす、ありそうでなかった「調性」本!!
目次
1 調性とは何か?―メロディからハーモニーへ
2 楽器からみた調性―得意な調と苦手な調
3 科学的にみた調性―自然倍音から音階、平均律へ
4 調性の歴史―聖歌から機能和声へ
5 調性に関するエトセトラ―東洋の調性から天体の音楽まで
6 それぞれの調性の特徴と名曲―長調、短調から微分音階まで
著者等紹介
吉松隆[ヨシマツタカシ]
作曲家。1953年(昭和28年)東京生まれ。慶應義塾大学工学部を中退後、一時松村禎三に師事したほかはロックやジャズのグループに参加しながら独学で作曲を学ぶ。1981年に「朱鷺によせる哀歌」でデビュー。評論・エッセイなどの執筆活動のほか、FM音楽番組の解説者やイラストレイターとしても活躍中。TV・映画音楽も多く手がけており、近年では2009年に映画『ヴィヨンの妻』(監督:根岸吉太郎)の音楽(第33回日本アカデミー賞優秀音楽賞)、2012年にNHK大河ドラマ『平清盛』の音楽を担当(第67回日本放送映画芸術大賞放送部門最優秀音楽賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。