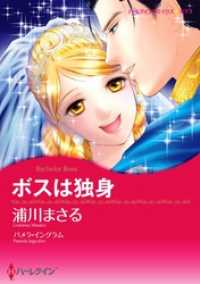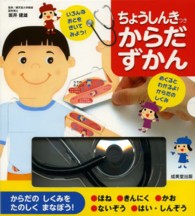内容説明
ボーカロイドはどのように生まれたのか?歌う技術の基本がまるごとわかる!生みの親による唯一の歌声合成解説本。
目次
1 VOCALOID前夜
2 VOCALOID1の開発
3 VOCALOID1で培われたVOCALOIDの基本技術
4 VOCALOID2の開発とテクノロジー
5 VOCALOID3の開発と機能
6 VOCALOID3に搭載された新技術
7 歌声ライブラリの制作方法
8 VOCALOID Editor for Cubaseとは
9 iOSを用いたiVOCALOID
10 進化するVOCALOIDと今後の可能性
著者等紹介
剣持秀紀[ケンモチヒデキ]
1967年生まれ。1993年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。在学中は京都大学交響楽団に所属し、数々の演奏会に出演。1993年ヤマハ株式会社入社。音響関係の研究開発に従事した後、1996年L&Hジャパン株式会社(ベルギーのL&H社とヤマハの合弁会社)に出向。テキスト音声合成技術の開発に従事。1999年復職。以降VOCALOIDを含む音楽・音声信号処理技術の開発に従事。現在、ヤマハ株式会社事業開発部yamaha+推進室VOCALOIDプロジェクトリーダー
藤本健[フジモトケン]
1965年生まれ。1989年横浜国立大学工学部電子情報工学科卒業。リクルートに15年勤務した後、2004年に有限会社フラクタル・デザインを設立。高校時代からシーケンスソフトの開発やMIDIインターフェイス、パソコン用音源の開発に携わってきた経験がある。リクルート在籍時代から社外でDTM、オーディオ、レコーディング関連の記事を中心に執筆しており、これまでも多数の関連書籍がある。現在はブログ型ニュースサイトDTMステーションを運営するほか、AV Watchの連載記事などを執筆している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
tuppo
satto
Mariyudu
calarud