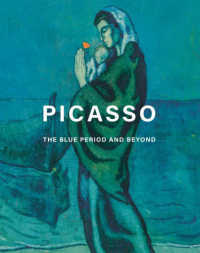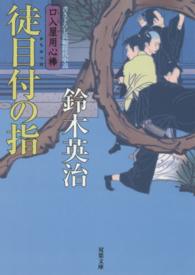内容説明
譜読みってなぜ必要?効率的な覚え方は?楽譜との向き合い方が根本から変わる!ピアノ教本研究家の著者が数々の教本から導き出した、「譜読み」を身につけ演奏を変えるための一冊!
目次
なかなか楽譜が読めない理由
ドレミの読み方をどうするか―「固定ド」と「移動ド」
欧米における譜読みの歴史
日本における譜読みの歴史
音感をつける
リズム読みの効果
五線の仕組みとドレミの場所を覚える
空間認知と譜読み
簡易楽譜を取り入れる
心の中で音を鳴らすために
理論を学び、パターンを見つける
本当の譜読み力を目指して
おわりに
著者等紹介
山本美芽[ヤマモトミメ]
音楽ライター/ピアノ教本研究家。東京学芸大学大学院修了。ピアノ教育とジャズ・フュージョンを軸に執筆、音楽誌『ムジカノーヴァ』『ジャズジャパン』などに寄稿。ピアノ教本研究家として全国で講演を行う。ピアノ講師としても指導に携わる。facebookで「山本美芽ライティング研究会」を主宰、多くのピアノ講師とともに次世代のピアノレッスンのあり方を追求、発信している。著書多数。ピティナ指導会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
96
13のステップより、欧米および日本の譜読みの歴史の方が興味深かった。ペスタロッチ主義がボストン音楽院に受け継がれ、そこに留学していた伊澤修二を通じて日本の唱歌教育が生まれる。園田清秀先生の「新しいバイエル」が日本の音感教育の源流になる。我々が慣れ親しんでいるリズム唱(タンタタ)が、試行錯誤を重ねて生まれた日本独自のものであったことも初めて知る。固定ド唱法のラテン系・東方教会系では調性感・和音感が、移動ド唱法のゲルマン系・北欧系では論理性が優先されるという説は、その相関の必然性がどうも納得できなかったが…。2021/12/09
kayak-gohan
16
私がピアノのレッスンに通っている音楽教室では弾く前に譜読みとリズム読みをするよう指導されている。それで何か参考になることがあるかもしれないと思って読んでみた。譜読みの歴史から始まって、実践的な指導方法が豊富な取材事例をもとに紹介されている。どちらかというと指導者向けの本。それでも、教わっている側の自分にとっても有用な記述もあった。2021/10/24
葉っぱかさかさ
7
楽譜の歴史からみるその必要性と変遷。音楽家にとっての譜読み、指導者からみた譜読み指導。何事にも絶対的な答えなどというものは無いのだと感じた。 個人的には新しい発見のない内容だったけれど、思い出したり再認識したり、自分の能力の特徴を掴むには無駄にならない感じがした。こういった本は読者が何を知りたくてこの本を手にしたか、ということが読後感に大きく作用するが、それでその本の価値が測れるわけでもないと呟いてみる。だからタイトルに惹かれたら読んでみるといい。読みやすいからね。うん。と、微妙な感想を書いてしまった。2022/05/09
あづさ/kyoka
6
幼児期から譜読みを教えるための、講師向けの本。自分自身も教わってきたことが体系的に書かれているので理解しやすかった。大人に教える・大人が覚える場合はそれまでに蓄積した知識や経験が人それぞれなのでこの通りにはいくはずもないが、使える手法はありそう。2022/03/24
AKO
3
分厚い本だけど意外とサクサク読めた。音楽教育の歴史を知りながら、譜読みの力のつけ方を改めて学べた。自分で言うと、子ども時代に楽譜読みに苦労した覚えはないけど、絶対音感がついたので、移動ドや移調楽器はしんどかった。吹奏楽スコアでも移調楽器はB管ならドをシ♭、ホルンはドをファと読み替えている。それは楽典やソルフェージュも学んだからできることなので、やはりそれらはピアノ教室でも大事にしていきたいと思う。弾くことだけではなく。まだまだ数えて読んでいる生徒や読むのが遅い生徒は気になるし頑張っていきたい。2023/09/12