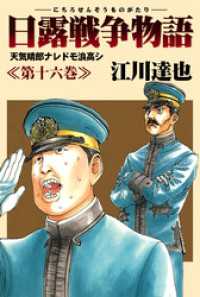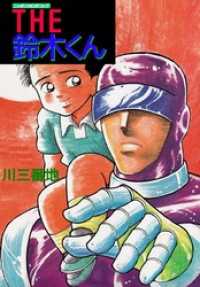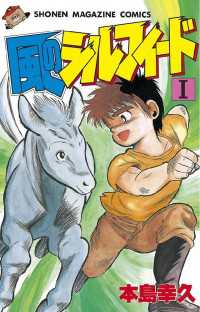- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
人は何をどう捕って、どう食べてきたのか。野兎やカラス、トウゴロウ(カミキリムシの幼虫)、ツチクジラなど、かつて私たちが享受した自然の恵みと原風景の記録と考察。
目次
野兎
鴉
トウゴロウ
岩茸
野鴨
鮎
鰍
山椒魚
スギゴケ
スガレ
ザザ虫
イナゴ
槌鯨
熊
海蛇(エラブウミヘビ)
海馬(トド)
著者等紹介
遠藤ケイ[エンドウケイ]
1944年新潟県生まれ。長年、自然の中で手作り生活を実践しながら、民俗学をライフワークとして、日本各地や世界各国を旅して、人々の生活や労働習俗を取材している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
40
歴史が始まって以来、人はいろいろな場所に暮らし、いろいろなもの(動植物)を食べて生きてきた。狭いようで広い、この国においえも然りだ。それは、置かれた環境の違いが大きな要因の一つでもあると思う。文化が違えば、食べるものも違うし、見方も違って当然だ。ここで取り上げられていることに共通するものは、そんな食べ物(動植物)への畏敬の念お、大切にいただくということ。先代から引き継ぎ、次の世代にも残すことを考えているということ。ここが大切なこと。2020/08/15
鯖
21
蓼のような苦い汁を出す植物も物好きな一部の虫は喜んで食べる。蓼のような生き物を食べ尽くす話。烏とか兎とか骨が多いのは全部鉈で叩きまくってつくねにすれば食べられるというのは金カムで学びましたチタタプチタタプ。イナゴとかハチの成体はいけるけど、幼虫はぷちゅってのがダメなんだよな私。ウルルンで小池栄子があまじょんかどこかに行って「普通に食える」って食べてた時に本気で尊敬した。さすが北条政子。トド等の海洋哺乳類は深く潜水するために筋肉中の血液量が多いので加熱すると黒くなるというのは知らなかった。面白かった。2021/06/20
ようはん
17
昔の日本人は自然から狩猟や採集で食糧を得るのが当たり前であったけど、それは命懸けの物であったのはこの本を読んでみて分かる。2021/12/11
ウミノアメ
5
生きるために食う、食うためには知恵と力を合わせて獲る、獲った命は大事にいただく、という自然の連鎖の中に人がいるということを改めて知らされる。 紹介される動植物は、普通は食べたことのない物ばがりだが、どれも入手の経緯から調理方法、民族的な考察まで興味深く読めた。 アウトドア好きな方にはおすすめ 2020/08/01
友川サイコー
4
山人。狩猟し解体し食らう。実にリアル。末尾に辺見庸の作品への献辞。この作者は追う価値がある!2020/07/11