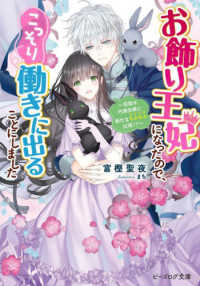内容説明
2014年9月27日午前11時52分、それまでの和やかな雰囲気は激変した。笑顔は消え、笑い声は悲鳴に包まれた。剣ヶ峰周辺には、250人ほどの登山者で賑わっていたが、火山ガスに覆われ、巨大な噴石が飛び交い、一瞬にして生死の境に放り込まれてしまった。御嶽山噴火とはなんだったのか―、頂上付近で被災しながらも生還した著者が、2年たった「あのとき」を振り返る。
目次
第1章 運命の一日(絶好の登山日和;十一時五十二分、一回目の噴火 ほか)
第2章 噴火の実態(御嶽山という山 ほか)
第3章 噴火の爪痕(困難を極めた捜索活動;取材と報道、伝えることの大切さ ほか)
第4章 噴火の教訓(生還できた理由;正常性バイアスと多数派同調バイアス ほか)
著者等紹介
小川さゆり[オガワサユリ]
1971年、中央アルプス、南アルプスが映えるまち、長野県駒ヶ根市生まれ。南信州山岳ガイド協会所属の信州登山案内人、日本山岳ガイド協会認定ガイド、中央アルプス地区遭対協救助隊員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
M
122
山岳ガイドである著者が下見の為に単独入山していて、あの噴火に遭遇。被災当事者かつ専門家ならではの、今後に伝承し続けたい「教訓」を切に書かれている。著者の被災した状況はまさに九死に一生を得たもので、生死が紙一重の過酷な中でいかに「命を守る行動」に徹したか。生きて帰るために何が必要なのか。「運が良かった」だけでは成し得ない「危機意識」の重要さをタフに説いている。登山をする方には必読の本。2016/12/25
kinkin
86
2014年御嶽山の噴火によろ多数の犠牲者が出た、山岳ガイドをしていた著者が当時の様子を伝える。日本は世界でも有数の火山国だ。昔は死火山、休火山、活火山と言われたが、現在では死火山というのは無いようだ。いつ爆発してもおかしくないという。当然その兆候はあるようだが。御嶽山の場合は爆発前に地震も起きており警戒レベルを上げていればと著者は書いている。他犠牲者のことや、報道に対する疑問点、教訓など。すこし冷静さに欠ける部分もあったが、そこは体験者でもあり本を書く仕事もしていないので仕方が無いと思う。図書館本2024/11/05
キムチ
57
下見だけで登山者として登った筆者、主観にポイントを置いた語り口。失礼ながら1~4章を経てスタンスや思いが変化していくのが逆に生々しく伝わる。報道に批判的口調になるのはやむを得ない~日本の報道は言語的教訓を伝達するのは不得手と言い切っている。我々が日常接するTV や新聞。雑誌インタビューでも「そこだけ切り取って」いう内容がいかに真実を捻じ曲げるか知る人は知っている。山をやらない人には臨場感が伝わってこないだろうけれど、その危機の現場で正常性バイアス=逃げ遅れの心理がどう働くかの説明はよく解る。2017/06/02
hatayan
54
2014年の御嶽山噴火の現場に居合わせ、奇跡的に生還した登山ガイドが2年後に教訓を記す一冊。噴火直後の噴煙にカメラを向ける登山者の写真があまりに突然の災害だったことを残酷に物語ります。 著者が生き残ったのは、とっさの判断と行動で死の影を振り切り、たまたま運が味方をしたからだったといいます。苦い思いを繰り返し反省することで危機を正しく認識できる能力が身につく。自然に踏み込むときは自己責任という強い意識と覚悟を持ちたい。 犠牲者や遺族に配慮しながら、あの場に居合わせた者にしか語れないことを伝えようとします。2020/02/26
♡ぷらだ♡お休み中😌🌃💤
51
御嶽山噴火の生存者の1人である著者が、生かされた自分にできることは、命を落とされた登山者の見た噴火の恐怖と、残していただいた教訓を伝えることだという。「危険に対する意識を変える」「正しく知り、正しく恐れる」「命がけであっても、命をかけてはいけない」「自分の命が守れなければ、人の命はまもれない」などが印象に残った言葉。2019/07/14