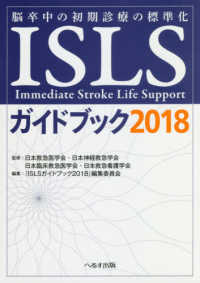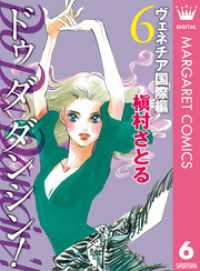内容説明
大量の情報や便利な登山用具があふれる現代。山の危険を知らないビギナーや、登山のキホンを忘れたベテランが、軽い気持ちで全国津々浦々の山へ向かい、その一部の人が道迷いの罠にはまっている。登山計画、現在地把握、リスク意識の保ち方など、基礎技術の面から再学習して、山の危険を克服する本当の力とは何かを考えよう。
目次
第1章 道迷い遭難の事例に学ぶ
第2章 さまざまな道迷い遭難の起こり方
第3章 低山での道迷い遭難の実態
第4章 道迷いを防ぐ登山技術“準備編”
第5章 道迷いを防ぐ登山技術“実践編”
終章 道に迷ってしまったら
著者等紹介
野村仁[ノムラヒトシ]
1954年秋田県生まれ。登山、クライミング、自然・アウトドアなどを専門分野とする編集者・ライター。登山技術、山岳遭難関連の執筆を長年にわたってつづける一方、クライミング関係では第一人者を著者に迎え、編集を担当して技術専門書を世に送り出してきた。編集事務所「編集室アルム」主宰、山の文化を研究する日本山岳文化学会常務理事、遭難分科会、地理・地名分科会メンバー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
68
登山の危険の一つ、道迷いについて実例と対策を記した一冊。自分は基本登山道の整備された山ばかりで道が解らなくなるような山に登ったのは数度なのだが、その山での経験を思い出してみると道に迷うのもむべなるかなと思う。基本として読図とビバーク知識が挙げられているのだが、前者は兎も角後者は未経験なため不安。写真付きで解説してくれているのはありがたい。あと引き返す勇気と迷ったときは下に下らない、この辺は先達からさんざん言われたなあ。ともあれ登山というと危険と隣り合わせである、という意識を常に持ちたいものです。2020/10/01
yamakujira
12
具体的な事例を挙げながら、道迷い遭難を考察して原因を探り対策を提言する。道迷い遭難を、地域的な側面から「近郊型」と「深山型」に分けたり、季節的な側面から「無雪期」「残雪期」「積雪期」に分けて考察するのはわかりやすい。記憶に新しい房総半島でのツアー遭難についても、一方的に批判しない冷静な考察と、後日トレースしたら自分でも迷うという正直な考証は、好感が持てるし信頼できると感じた。山を歩くときには他人事と思わずに気をつけたいね。でも、道に迷うなんて人間だけ、生物として退化じゃないかと不安になる。 (★★★☆☆)2017/06/04
imagine
7
山の怪異や山間部での生活について知るほどに、登山技術にも興味を持ったので。道迷い遭難は低山ほど起こりやすいそうで、本の冒頭から具体例がいくつも登場。自分が登山した場所でも複数の事故が起きており、他人事ではないと思い知らされる。その一方で、遭難者に対して寛大な見解を示し、地形図の使い方やビバーク技術を紹介してくれる。登山の魅力自体が読み手にしっかり伝わり、山に誘われているかのような読後感。2018/11/21
LaVieHeart
6
登山者がどのようにして道迷い遭難に至ったのか、著者ご自身で検証もしつつ、非常に分かりやすく為になった。登山地図に慣れきった私には、地形図の読み方はちょっと難しくてよく分からなかったけども。 低山ほど迷いやすいというのは、実際に私も林道に迷い込みそうになり、YAMAPと先人のピンクテープがなければ完全に迷うところだったとキモを冷やした事がある。 とにかく、山は高低を問わず油断しない事、違和感を感じたら転倒・滑落に気を付けて早いうちに戻る事、沢には降りない事、これは誰のどの本でも言っている、鉄則である。2024/08/23
Narumi
5
自己啓発本みたいなタイトルですが、これは比喩ではありません。道迷い事例の一つ一つがけっこう細かく解説されていてわかりやすいです。また、道に迷わないためのプランの立て方や装備なども非常に具体的。登山にはたぶん行かないと思いますが、ちょっとしたハイキングなどに行くときも参考になりそうです。登山地図というのがあるそうで例が載っていますが、ものすごく至れり尽くせりで驚きました。ただ、道などがあまりにも整備されて過ぎているのも道迷いの一因では?という著者の苦言も。2019/09/02