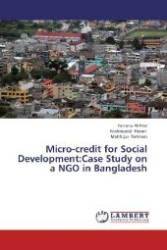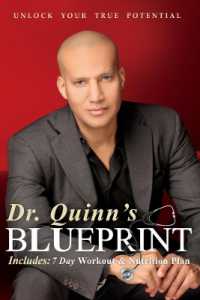内容説明
昔から日本の山は宗教と深く結びついている。山名や地名の由来はもとより山が与えてくれるパワーの存在を知れば知るほど山が好きになるに違いない。
目次
第1章 山の神仏についての雑学(山を数える単位は、なぜ一座、二座なの?;人はなぜ、山を敬うのか? ほか)
第2章 主な神さまと山(神さまって何ですか?;筑波山に鎮座する、イザナギとイザナミの神 ほか)
第3章 仏教に学ぶ登山の知恵(仏教に学ぶ安心登山の知恵;憧れの山に登るためのお釈迦さまの教え ほか)
第4章 山岳宗教と密教(山岳修験道とは何か?;修験道発祥の地・金峯山寺と役行者 ほか)
第5章 山で神仏を感じる(北海道の山々で、カムイを感じる;神仏の魂が宿る植物 ほか)
著者等紹介
太田昭彦[オオタアキヒコ]
1961年東京生まれ。高校ワンダーフォーゲル部時代に登山の魅力に目覚め、社会人山岳会で経験を積み、34歳で旅行業から山岳ガイドに転身。42歳で巡礼先達の道を歩み始める。歩きにすと倶楽部主宰。日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド。四国石鎚神社公認先達。四国八十八ヶ所霊場会公認先達。京都洛陽三十三観音公認先達(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
102
上高地から真っ白い穂高連邦を見たとき、なにか恐れに似た感覚にとらわれました。それが自然に対する畏敬の念だったのですね。登山ガイドである著者は、それは神様の存在を感じることだと言っています。普段の生活では神様を感じることはあまりありませんが、山の中では神様を感じやすくなるようです。山登りがいっそう楽しくなりそうです。この本は神仏に関する起源や人との関わりを解りやすく説いていて、山好きでなくてもたいへん参考になります。「ご来光の発祥は、阿弥陀様だった」「空海と山岳信仰」など、仏教のお話もたっぷりとあります。2020/08/05
Shoji
74
日本人は万物に神が宿るとする宗教観を持っていて、山や木や水に神が宿ると考えることに違和感を持っていません。また同じく仏教においても、鎌倉密教や修験道のように山を宗教の対象と捉えてきました。この宗教観にも私たちは違和感を感じません。この本は、レクリエーションとしての登山をモチーフにして、平易な言葉で山岳信仰を分かりやすく解説しています。出てくる山もメジャーな山ばかりです。楽しく読むことが出来ました。2017/12/12
ゆみきーにゃ
54
《職場》読みたい本に登録してあったけど、何でだろう?もっと神さま仏さまメインで書いてあるかと思ったけれど、山登りについてがメインだった気がする。山登りはしないので、山の名前を見てもどこの山かほぼわからず残念。どの山のことかわかった上で読んだらすっごく楽しかっただろうな~2017/03/15
ykshzk(虎猫図案房)
22
「自然は神が造ったもの」ではなくて「自然そのものが神」というのが、日本人の自然観の根底にあるという著者の意見には頷ける。仏教・神道と山の関係は深く、修験者にとっては山は修行の場であり、里山に暮らす民にとっては身近な山は神聖な場。亡くなった人は山にかえり、春には山から里に神が来て秋には山に帰っていく(春秋去来)。そしてそれは春と秋の祭りにつながるなど、山は日本人の文化ととても深く繋がっている。いつも山歩きの際はどんな植物に出会えるかで頭が一杯になってしまうが、今度は山そのものを敬う気持ちも持って歩きたい。 2024/06/24
あまね
15
何がなく手に取った本ですが、とても良かったです。山岳ガイドの著者の優しさが滲み出ている本でした。神社の奥宮に参拝することは憧れているので、チャレンジしたくなりました。2021/02/07
-

- 和書
- 現代社会福祉の諸相