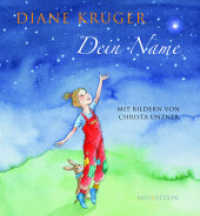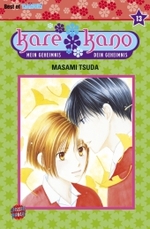内容説明
日本の海外登山史上最悪の遭難から15年。長きにわたる遺体捜索活動を乗り越え、そこで出会った「聖なる山」の真の姿とは…。
目次
1章 聖山への登山(遭難(一九九一)
再挑戦(一九九六) ほか)
2章 カワカブとの出会い(チベット人の村に暮らす;梅里雪山一周の旅)
3章 四季の梅里雪山(魔の山、聖なる山、そして豊かな山;カワカブ巡礼 ほか)
4章 森と氷河を巡る(松茸の香り;カワカブの森へ)
5章 聖山とはなにか(聖山に出会う旅;六〇年に一度の巡礼 ほか)
著者等紹介
小林尚礼[コバヤシナオユキ]
1969年、千葉県生まれ。京都大学工学部卒業。大学では山岳部に在籍し、日本各地の山に通う。1996年の梅里雪山登山を機にフリーカメラマン・ライターをこころざし、雑誌などを中心に撮影・取材活動を行なっている。撮影のテーマは、「人間の背後にある自然」。また、チベットでの長期滞在の経験を元にして、ヒマラヤ・チベットを中心とした山旅のガイドも手がける。(社)京都大学学士山岳会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マリリン
44
きっかけは遭難した仲間の捜索に参加した事。聖山(カワカブ)は神の領域。国内にもこういう場所はあるのではと感じた。人間に容赦なく自然を突きつけ拒むだけではなく、この地と人々との関わりに微笑む姿も見たような気がした。遭難した友の捜索の経緯や現地に住む人たちの生活事情も書かれているが、著者が長い時間をかけ丁寧に真摯に自然と向き合い、現地の人々の文化や信仰等を受け入れ接した姿勢に惹かれた。2022/04/13
ニンジン
27
タイトルで遭難事故のドキュメンタリーかと思いましたが、梅里雪山を聖なる山として崇める地元の方々との交流が描かれていました。 著者も初めは山を「征する」気持ちがあったのですが関わっていくうちに認識を改めていく様が印象的でした。 良くしていただいた村長は今もお元気だといいなぁ。 残る一人も早くご家族の元へ帰れる事を祈ります。2021/09/21
taku
15
その姿、まさに美しき峰ありて。多くの巡礼者を引き寄せる信仰の山。登山家は残念だろうが、未登峰のままであるべきかも。91年、雪崩の直撃と推測される事故で遭難した、日中合同学術登山隊17名の遺体捜索活動を著者は続ける。その状況や遺体、素晴らしい風景、麓の村落や住民の写真に、生と死、山と人の有り様を思い描く。村の生活を見つめ、自ら巡礼を行い四季を見つめ、氷河と森を巡り、聖山という存在、人との関わりを肌で感じ著者は悟る。これまで読んだ山岳本とは異なる余韻が残った。 2022/01/28
katerinarosa
8
登山家の人達の本を読むと、山は征服するものと考えている人が多いことに気が付いた。特に海外の登山家なんかはそれがとても顕著に出ている。日本人は富士山をはじめとして山岳信仰が文化に根付いているので、地元民が聖山として崇めている気持を理解することが、他国人に比べて容易なのではないかなと思う。著者も征服するものと思う一人で、遭難した登山チームの捜索や遺族とのやり取り、第二次派遣隊の一員となり天候不順などでアタックを断念して下山する前半部分においてはそれが顕著。ところが後半部分に入っ2016/02/19
sumitarou
4
遺体捜索にあたり協力をしてくれた麓の村人との交流が克明に描かれる。特にチャシ村長がとても魅力的な人物。霊山を侵そうとした(←表現が微妙ですが)遭難者の遺体は忌み嫌われる中、若き村長の協力の元で捜索を進められた経緯には、敬意を感じます。「チベットの村長」というと白髭の老人を思い浮かべるかもしれませんが、30歳台の壮年の男性です。若くして村を背負ってたつ人物の人間性の深さなどを感じます。2013/08/27