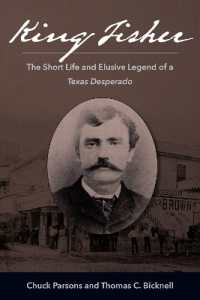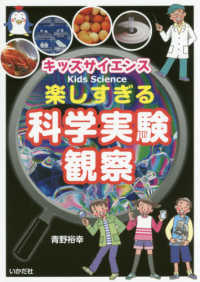- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
1970年7月、日高・カムイエクウチカウシ山で起きた悲惨なヒグマ事故を教訓にして、最近、増え続けるクマの事故を検証し、未然に防ぐ方策に迫る―。
目次
第1章 日高・カムイエクウチカウシ山のヒグマ襲撃事故
第2章 インタビュー 地元猟師が語る、秩父のクマの今
第3章 近年のクマ襲撃事故(雪山に出没したクマ(上越国境・仙ノ倉山)
畳平駐車場襲撃事故(北アルプス・乗鞍岳)
休日の山頂付近に現われたクマ(奥多摩・川苔山)
子連れグマ襲撃事故(滋賀・高島トレイル)
山菜取りの連続襲撃事故(秋田県鹿角市の山林)
里山に出没したクマ(奥武蔵・笠山))
第4章 クマの生態と遭遇時の対処法(ツキノワグマとヒグマの生態;最近のクマの出没と事故;人身事故増加の背景;クマとの付き合い)
著者等紹介
羽根田治[ハネダオサム]
1961年、埼玉県浦和市(現さいたま市)出身。フリーライター。山岳遭難や登山技術に関する記事を、山岳雑誌や書籍などで発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆活動を続けている。2013年より長野県の山岳遭難防止アドバイザーを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
109
山でクマに遭遇して襲われた6つの事例を取り上げて検証するとともにクマの生態と遭遇時の対処法が書かれていた。以前にも同じような観点から書かれた本を読んだことがある。人はなぜクマに襲われるのか、それは当たり前すぎるがクマと遭遇するからだ。だから本書には遭遇しないことがいちばんだと書かれている。そのためにはクマのテリトリーに近づかないことも大事だという。獣害というけれど人がクマのテリトーに入ってタケノコや山菜を採る。クマからみれば人害かもしれない。悲惨な事故に遭わないために知っておきたい事だ。 2017/12/13
NADIA
68
やーもう、マジ怖いからクマの話は苦手💦「大丈夫!!私は週末ハンター(@モンハン)だから、アオアシラ(クマのモンスター)だと思えば楽勝よ」と自己暗示をかけて挑んだ(笑) しかし、有名な福岡大学ワンダーフォーゲル部の3人死亡事故から始まる羽根田さんのドキュメンタリーはクマの恐ろしさを強調するものではなく、人間がクマのテリトリーに入り込んでいるということを意識させるものだ。これも山に入る人には是非とも読んでもらいたい一冊である。私は引き続き、クマに遭わないように山には入らない生活を送ろうと強く思ったよ。2022/08/10
HANA
59
山での遭難というと天候や事故に目が行きがちだけども、本来山は彼らのテリトリーであるという事を思い出させてくれる一冊。本邦の熊による遭難では外せない福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の事故を始めとして、漁師の語る熊との向き合い方、近年起きた熊による事故、生態と遭遇時の対処と熊を知る上で至れり尽くせりの本となっている。読み終えて思うのは熊もまた被害者であるという事。宅地化や登山によって彼らの領域に入り込む事、山に杉を植えた事などの要因が重なり事故の増加につながっているのであるな。怖いけど何か切なくなるような。2020/09/10
えんちゃん
58
山岳ライター羽根田氏によるクマ遭遇事例と対処法。最近クマのニュースが多いので手に取ってみた。クマと人間の軋轢の歴史と傾向。パニックに陥り暴れるクマはパニックホラー映画よりも何倍も恐怖だ。登山が怖くなる。丁寧な取材と現場の声とデータの数々。とても興味深く勉強になる一冊。2021/05/23
キムチ
50
羽田さんのペンは実にリアル・・まるで現場を俯瞰しているかのようで、恐怖がじわっと来る。ツキノワも羆も理屈抜きで怖い!友達が去年カムエクに行ったのでむむっと考えたが、勿論却下。安易に考えていた高島トレイルも止め。九州と四国は「いない」と言われるが。金剛と槇尾山もいないので安心して歩いている。大峰、台高はいるから怖いよぉ。秩父山系の事例から考えられることを語る猟師の言葉は正鵠を射ている。唐辛子スプレー、メンバーで歌を歌う、クマよけ鈴。。やはり、正解じゃないんだ。森のくまさん・・なんて唄うのはやめよう・・2018/03/16