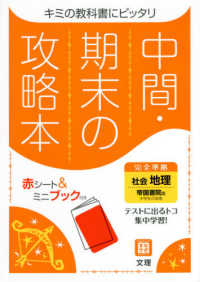目次
1章 こうして私たちは「顔」をもった
2章 アジア人はなぜベビーフェイスなのか
3章 赤ちゃんをかわいいと思うわけ
4章 ホモ・サピエンスの顔かたちの多様性
5章 顔かたちの違いは偶然か、それとも必然か
6章 日本人の顔かたちの特徴
7章 日本人のルーツ
8章 違っていることの重要性
おわりに―さらなる謎に向けて
著者等紹介
溝口優司[ミゾグチユウジ]
1949年、富山県生まれ。国立科学博物館前人類研究部長、理学博士。1973年、富山大学文理学部卒業。1976年、東京大学大学院理学系研究科中退/国立科学博物館人類研究部研究官。2009年、人類研究部長。2014年より名誉研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
91
日本人の顔の特徴は、突出していない鼻、幅広の頬、一重まぶたの平坦な顔であるが、これは北アジアの厳しい寒さに適応したという寒冷地適応説で説明できる。そもそも生物に顔はなかったが、感覚器を集めた顔を進化の過程で手に入れた。ヨーロッパでも日本でも約1000年前から短頭化が始まり、日本人も東西の地域によって顔形に違いがある。現在も気温などの環境によって変化し続けているのが顔なのである。今後、縄文人の核DNAの研究により日本人のルーツがわかる知見が楽しみ。国立科学博物館前人類研究部長の最新の知見であり興味深い世界。2021/04/11
yamatoshiuruhashi
39
「アフリカで誕生した人類が日本人になるまで」の著者による「顔」の形成についての本。とは言え本質的には共通する内容で「どうしてこのような顔になったのか」という問いに環境適応を中心に解を示す。本書も非常に読みやすくワクワク感を持って読めた。その考えの裏付けとなるDATA集めについて、自分が直接調べた頭骨の数値のみならず、何か数値が書かれている様々な国の幅広い文書に書かれた測定値を集める作業に数十年、PCに取りまとめるのに数年、ソフトを使っての解析にほんの数分という話に、そのプロセスへの敬意を禁じ得ない。2021/03/19
たまきら
29
なぜ顔ができたのか。進化の過程で私たちが得た様々な特徴。人類、そして日本人の「顔」がいかに環境によって培われたものかが説明されて興味深かったです。見た目を左右するDNAがどれかわかっている、とか、楽しい研究情報満載。娘と夫の臼歯が虫歯になりやすいのではと歯医者さんに心配されているのですが、カラベリ結節の説明があってああ、これみたいなものなのか!とびっくり。シャベル歯はアメリカンインディアンの友人が教えてくれたなあ…。面白かった。2021/06/07
美東
15
159頁 ”第8章 違っていることの重要性” このタイトル自体は問題ではないが、冒頭 ”違いに善悪も美醜もない” との見出しが置かれている。「芸術や文化の完全否定だ」と、私には思えた。以後、著者の主張は迷走しているように思う。 2022/01/20
hal
15
人類の顔がどう変化していったかに関して、一般向けに優しくまとめている。アジア系の顔が平坦で一重まぶたなのは寒冷地仕様とか。ヨーロッパ系と日本人では骨から違うらしいとか。結局、何故変わっていったかとか詳しいことはまだわからないという結論です。2021/03/11