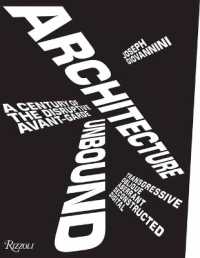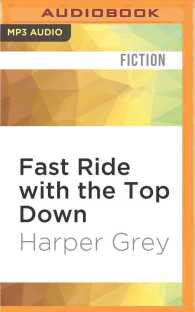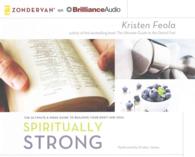内容説明
怪奇幻想文学専門のアンソロジストとして知られる東雅夫の編纂による、登山家たちが実際に山で出遭った「異界」の物語。「不思議な山」(夢枕獏)、「山の怪談」(深田久彌)、「焚火をかきたててからの話」(上田哲農)、「木曾御岳の人魂たち」(西丸震哉)、「夢」(串田孫一)、「七不思議」(辻まこと)ほか全26作。巻末に、編者解説収載。
目次
不思議な山(夢枕獏)
山の怪談(深田久彌)
焚火をかきたててからの話(上田哲農)
木曾御岳の人魂たち(西丸震哉)
谷底の絃歌(大泉黒石)
山で見る幻影(下平廣惠)
怪談「八ガ岳」(片山英一)
幻の山行(西野喜与衛)
夢(串田孫一)
山のおばけ座談会(山高クラブ)〔ほか〕
著者等紹介
東雅夫[ヒガシマサオ]
1958年、神奈川県生まれ。雑誌「幻想文学」(幻想文学会出版局/幻想文学出版局/アトリエOCTA)の編集長を創刊から終刊まで務める。その後、文藝雑誌「幽」(メディアファクトリー/KADOKAWA)の編集長と編集顧問も、創刊から終刊まで務めた。そのかたわら怪奇幻想文学専門の研究者・評論家としても多方面で活躍。アンソロジストとして、埋もれた作品の紹介も数多く手がけている。代表作に日本推理作家協会賞を受章した『遠野物語と怪談の時代』(角川選書)のほか、『百物語の怪談史』(角川ソフィア文庫)『文豪たちの怪談ライブ』(ちくま文庫)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
東谷くまみ
36
「科学でわかっているのは全体の2%にすぎない、知られざる世界こそ現実である」ノーベル物理学賞受賞の湯川先生の言葉。これこそ私が民俗学や異界の物語に惹かれる理由なのかも😆登山家たちが実際に体験した、不思議で怖い本当の話を集めた山岳奇談アンソロジー。今は登山というとメジャーだけどこの作品の舞台は明治~昭和初期にかけてのものが多く、山への畏敬の念や神秘性が今よりも深かったのかもな。ツチノコや妖系の話もあってワクワクしたけどゾッとするのがほとんどw中でも「炭焼きの話」は終盤まで引っ張られて怖かったけど面白かった2024/08/28
ワッピー
32
オール・ハロウズ・イヴHorror読書会'24参加本。ヤマケイの山怪系4冊目。明治から現代までの作家を網羅した山の実話怪談を収録。登山家やマタギの遭った怪異、飛ぶ光物・人魂、UMA譚、妖怪、山の神と幅広く網羅して平地とは違う空気を届けてくれます。とりわけ西丸震哉の人魂捕獲チャレンジと冷静な観察眼、あるいは自由人・辻まことが遭った怪異に驚愕!末尾の「山村民俗随談」(柳田国男)で様々なトピックから広がる奥深い民俗世界に憧憬の念を抱きました。ホラーとはいいにくいですが、山怪シリーズの中で一番楽しめた一冊です。2024/10/26
田中
26
昔に刊行された山岳雑誌や書籍類から抜粋した話しを収録してある。山で起こった不思議な怪異譚は好みなので手に取ってみたが、明治や大正時代のものが大部分で、そのため古い当時の文章や語句が馴染めなかった。民話風な怪談の趣があり、恐い実話本なのかと聞かれたら首肯しがたい。。。奥会津の山中での神隠しの話はなかなか興味深かった。忽然と消息を絶ってしまう現象は山の神秘性だろう【日本の夏は、やっぱり怪談】。2024/09/14
ネムコ
20
最近の読みやすい実話怪談に慣れていたので、かなり歯応えがありました。2024/03/02
春風
12
岳人が体験した・聞いた、山の怪談実話を集めたアンソロジー。平地にはあるべくもない寂寥感が幻覚を惹起するのか。はたまた。本作に収録される小品の多くが昭和前期に物されたものであり、懐旧譚ともなれば明治期まで時代が遡ることとなる。であれば、ただでさえ寂寞たる山は未開の趣がなお濃くなり、恐い。また山で出会う人ならざる者はよく笑う。笑うだけで物凄くなるのは、山という舞台装置のなせる業であり、山の本質の一側面なのだろう。小説家だけでなくエッセイストなど多岐に亘る職柄の岳人の実話怪談を収録した名アンソロジー。2023/03/24