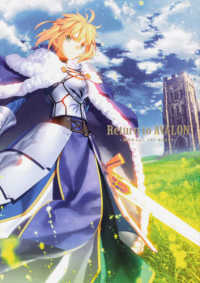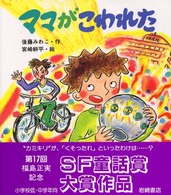内容説明
北海道の大地に生き、日高の山々を愛した画家・坂本直行の若き日の画文集。昭和初期、日高山脈を望む十勝平野の開拓牧場で、厳しい開墾労働の日々をおくりつつ、家畜や野生動物との触れ合い、開拓農民の生活、終生愛し続けた原野の自然と日高の山々への思いを、みずみずしい筆で描く。
目次
山・高原・牧場(牧場の冬;春の歌;夏の歌;秋の歌;冬の序曲)
飯場の話
著者等紹介
坂本直行[サカモトナオユキ]
1906(明治39)年釧路に生れる。札幌二中(現、札幌西高)から北海道帝国大学農学実科に進み、27(昭和2)年卒業。在学中は山岳部員として活躍。東京で園芸に従事したのち、29(昭和4)年、北海道に帰り、翌年から十勝平野の広尾で友人が営む野崎牧場で働く。さらに36(昭和11)年、同じ町の下野塚の未開拓地に入植し開拓に従事。34(昭和9)年1月、日高山脈コイカクシュサツナイ岳などに初登を記録、また37(昭和12)年1月、厳冬期ペテガリ岳をめざす北大隊に参加するなど、登山活動も行なう。困難な生活の余暇に日高など北海道の山野を主題に、絵筆をとり続け、雑誌「山」などに作品を掲載する。60(昭和35)年、画業を認められて山岳画家として立ち、農業から離れる。ネパールにもスケッチ旅行し、作品を残す。82(昭和57)年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さゆう
2
北海道を訪れた時、雪冠の山々を見て、全部富士山に見えると言ったら笑われたことを思い出した。アルバイトで畑の雑草取りに参加したら、畑の端が見えずに途方に暮れたこともあった。著者のように原野と格闘するようなことは無かったければ、大地がただただひたすらに続きくのが北海道だと記憶している。2023/04/05
徳島の迷人
1
1930年代、日高山脈東麓の牧場の四季の生活を純朴に記録する。登山好きでもある著者が、父の反対を押し切って友との牧場経営に乗り出す。発動機はあるがまだまだ普及しておらず、牛馬の力に頼る時代。様々な生物と自然現象と同じ人々との強い関わりも書かれる。半年も続く冬の厳しさは南の人間には閉口しそうだが、冬ならではの美しさや感覚も克明に表現されている。機械が出てこない景色を描いた水彩画からは、冷たくて爽やかな風すら感じそうだ。牧場経営は大変な割に貧しいが、嬉しい副産物も多い。「合理主義は人生の万能薬じゃない」2022/04/03
Kudo Atsushi
0
元のタイトル「ある牧場の生活」の通りで、登山中心の話ではない。2025/03/27
nishi
0
素晴らしい、住んでみたい 2024/11/29