内容説明
近代化により、伝統的な山の生業は一変し、高度経済成長を前に、林業は変容を迫られていた。「何千年も続いてきた歴史のそのような崖っぷちで、いわば山びとの最後の走者としての位置に、いま自分はおかれている」。先祖代々、炭焼きの家に生まれ育った著者が、山仕事のかたわら自らペンをとった。自叙伝であり、昭和の林業史をなす。昭和55年刊行の作品。
目次
序章 古窯の跡を訪ねて
第1章 炭焼きと植林
第2章 青春の西ン谷
第3章 果無山脈の主
第4章 十津川峡春秋
第5章 食物記
終章 果無山脈ふたたび
増補 新しい世紀の森へ
著者等紹介
宇江敏勝[ウエトシカツ]
1937(昭和12)年、三重県尾鷲市の炭焼きの家に生まれる。和歌山県立熊野高校卒業後、紀伊半島の山中で林業に従事するかたわら、文学を学ぶ。作家、林業、熊野古道語り部。文芸同人誌『VIKING』同人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
33
紀伊半島で山を生業とした作者の山仕事記録です。戦後から昭和50年代にかけての栄枯盛衰が書かれています。小屋掛けをして炭を焼いた若年期、山を開き飯場を建て原生林を大規模伐採した青壮年期、時代に押され山を下りる老年期が綴られています。豊かな原生林を皆伐し杉や桧を植林した時代には面白いように儲かったであろうが、今となっては残念だ。手に負えない大木は、木の皮を剥いで枯れ死させたそうだ。そうして山を裸にして杉や桧を植えたとか。それが当時の国家緑化運動だったそうだ。現代の価値観では考えられない。残念な昭和の話でした。2022/01/15
booklight
27
1937年生まれの筆者が、紀伊半島で炭焼の一家に育ち、林業に携わってきた半生を振り返る。ある山で炭焼をすることになると、適した地を選んで、切り開き、仮家を建て、窯を作り、木を切って炭にする。そして次の山に移る。そんな昔から続く山暮らしが、エネルギー革命で炭が使われなくなり、山仕事は林業・植樹に移っていく。人に好まれない山仕事を筆者は気に入って、様々な山での植樹を行う。しかし林業は廃れ、管理されなくなり、山は荒廃。山仕事の現場の遍歴がよくわかる。かつて一家で作った窯や自分が植樹した山を訪れる様子が感慨深い。2021/12/12
jackbdc
11
約40年前に世に出た名作の復刻版を初。炭焼や営林など山仕事に従事しながら作家として知られる著者のデビュー作。大正から戦後、現代に至る山で働く人々の実情を覗く事が出来るドキュメンタリーとして貴重な作品。最も印象に残った3点は、1.山仕事の多様性:花形は狩猟採集・木挽→炭焼き→営林→土木へ変遷か。2.国家政策との関連:エネルギー需要(石炭や石油)や輸入品との競合の影響を強く受ける側面を実感。3.文化伝来速度の波形と未来:時代の波が都市→里→山へと順々に伝播して来た事がわかるが、未来は山村が先行する側面もある?2022/04/30
maqiso
6
家業の炭焼きから造林業に移り、里にもあまり帰らず林業の変化を見続けている。造林は景気に左右されたり機械化されたりしても山にこもる肉体労働なのは変わらず、消えゆくのもわかる。紀州と吉野食べるキノコが異なるの面白い。2022/04/13
kitakama633
2
貴重な、失われてしまった記録だが、文章もよい。宮本常一著作集と並べて、著者の作品も集めてみよう♪2024/04/19
-
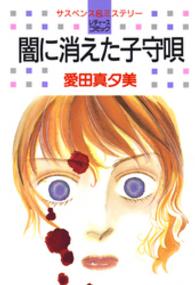
- 電子書籍
- 闇に消えた子守唄 白泉社レディース・コ…
-
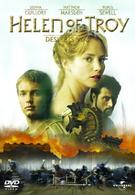
- DVD
- トロイ・ザ・ウォーズ






