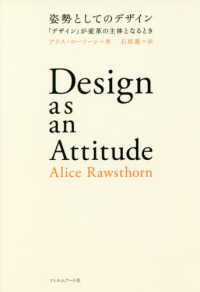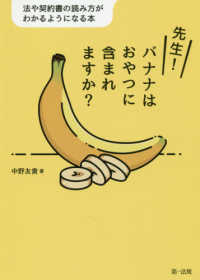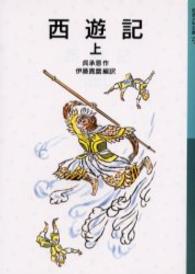内容説明
昆虫や鳥を呼び寄せ、厳しい環境に適応するために咲く花。人間の生活を豊かにし、ときに歴史を大きく動かしてきた花。それぞれの花が知恵と工夫で生き抜く姿を、愛あふれるまなざしで語る植物エッセイ。
目次
春(人々を魅了してやまない一瞬の美しさ―サクラ(バラ科)
田んぼ一面に咲く花に隠された共生関係―レンゲ(マメ科) ほか)
初夏(美しく複雑な形はハチを呼ぶ戦略―ハナショウブ(アヤメ科)
名前と分類に翻弄されても美しく咲く―アヤメ(アヤメ科) ほか)
夏(世界初の麻酔手術に使われた花―チョウセンアサガオ(ナス科)
日本の寒さになじんで愛される南米の花―ペチュニア(ナス科) ほか)
秋(ピンクの語源になった花―ダイアンサス(ナデシコ科)
中国でも重用される草木の中の君子―キク(キク科) ほか)
冬(もともと香りのなかった内気な花―シクラメン(サクラソウ科)
本当はクリスマスが似合わない植物―ポインセチア(トウダイグサ科) ほか)
著者等紹介
稲垣栄洋[イナガキヒデヒロ]
1968年静岡県生まれ。静岡大学大学院農学研究科教授。農学博士、植物学者。農林水産省、静岡県農林技術研究所を経て、現職。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。