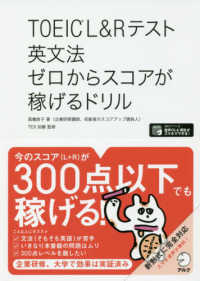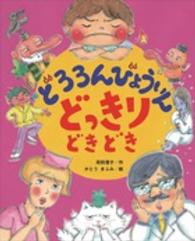内容説明
熊撃ち、ボッカ、山小屋主人、イワナの養殖師、修験者、木地師、職業的釣り名人…。みずから山で生きることを選択した人びとの半生を描く、十三編のルポルタージュ。一九八六年に刊行された作家・甲斐崎圭氏の名著に、一編を加えて、文庫で復刻。三十年の時を経て現在、貴重な記録であるとともに、極度な非身体的生活環境と化した現代への問題提起ともなっている。
目次
北の山の羆撃ち―行方正美(北海道)
北涯の森の探究師―青井俊樹(北海道)
阿仁のマタギ―松橋時幸(秋田)
絶壁の岩茸採り―松本源一(群馬)
白馬岳のボッカ―太田健三(長野)
浅草生まれの山小屋主人―嶋義明(長野)
イワナの養殖師―池田留雄(滋賀)
修験者の宿坊守―五鬼助義价(奈良)
大峯に賭けた父と子―赤井邦正(奈良)
最後の木地師―新子薫(奈良)
北山の老猟師―勝山倉之介(京都)
京都修道院村―日向院主と八人の村人(京都)
職業的釣り名人―松岡武雄(岡山)
著者等紹介
甲斐崎圭[カイザキケイ]
1949年、島根県生まれ。作家。自然と深く関わりながら生きる人びとのルポルタージュを主に手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
80
山暮らしに人生を賭けた13人の男たちのドラマ。山、山は苦手。何と言っても登らなければならないうえに前や周りが見えない。生き物の鳴き声がするが姿は見えない。川沿いをを歩くとマムシも潜んでいる。海育ちのせいなのか山はやっぱり馴染みがない。しかし本書にはマタギや釣り師、ボッカー、木地師他山を縦横無尽に駆け巡る男たちばかりだ。。そんな男たちの話は好きだ。最近ヒグマや月の輪熊のマタギの本を何冊か読んだ。ヤマケイ文庫の本はそんな話で楽しめる。図書館本。2024/03/04
ちぃ
17
昔ながらに山に生業を求めてきた人たちの話ばかりでなく、宿坊や修道院、山小屋などいろいろな形で山に暮らす人たちのストーリー。レジャーで行く山と、仕事で山に入る人たちとの体験する世界には隔たりがあるんだろうなぁ。2021/08/02
CTC
10
15年ヤマケイ文庫、初出は80年〜86年の『山と渓谷』他月刊誌、書き下ろしが2本収録されていて、そのうちの1篇が本書の白眉(岩茸採りの話)。本書はマタギや川漁師、木地師など山に生きた13人にそれぞれ著者が会い、その様子を記すもの。取材から30年以上が経過している訳だから、故人も多い(各章末に文庫刊行時の注あり)。ググってみると甥っ子が継いだ山奥の宿坊が現在は2食付き8,000円で繁盛していそうな気配のケースもあるが、継ぐものなく今はネットで廃墟村として著名化している山寺もある。昭和はやはり遠くなりにけり。2019/05/17
yamakujira
9
「山人」を紹介する13編のルポ。ここで言う山人とは、山に暮らすこと、山に生きることを選択した男たちで、猟師、演習林助手、岩茸採集者、ボッカ、山小屋の主人、養殖業、宿坊の主人、木地師、宗教家、釣り師など、その生業は多岐にわたる。どの男にとっても山は娯楽の場ではなく、まるで人生の軌跡が山そのものであるような迫力がある。本書は30年前に刊行された底本に、未収録の1編を加えて復刊したらしい。章末に他界を伝える注釈が添えられた人も多い一方で、注釈が一切ない人に、むしろ市井の名もなき男の人生を感じた。 (★★★★☆)2015/12/30
ぷかり
5
山は山。人は人。2017/11/11