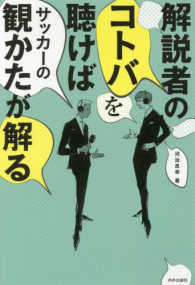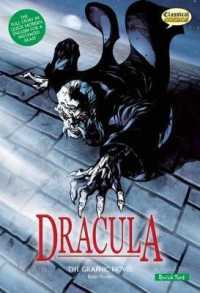内容説明
1977年8月、山好きの一匹狼たちの寄せ集め集団が、エベレストに次ぐ世界第2の高峰K2の日本人初登頂に成功した。正統派と言われる日本の登山界を尻目に、反目とエゴをむきだしにしながらのアタックだった。個人と組織の間で苦悩する登山隊長ら幹部の焦燥、登頂への執念をひたすら燃やす隊員たちの葛藤―。日本の高度経済成長を背景に、あまりにも人間的な登山隊員たちの姿を描いたノンフィクション。
目次
幻の白い峰
一匹狼たちの集団
登山家の宿命
出発前の難問
登頂隊員への先陣争い
氷と岩のバルトロ街道
隊員たちの反目とエゴ
K2の頂上に立つ
喜びと恨みと怒りの下山
「自分の山」めざして
著者等紹介
本田靖春[ホンダヤスハル]
1933(昭和8)年、旧朝鮮・京城に生まれる。55年、早稲田大学政経学部新聞学科を卒業し、読売新聞社に入社。社会部記者、ニューヨーク特派員などを経て、71年退社。その後、ノンフィクション作家として文筆活動に入り、活躍。77年、『誘拐』で文藝春秋読者賞、講談社出版文化賞、84年、『不当逮捕』で講談社ノンフィクション賞を受賞。潮賞、大宅壮一ノンフィクション賞の選考委員を務める。2004年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ビブリッサ
69
山好きにも正統派がいる。正統があれば異端がある。そんな奴らがK2に挑み、その強情さを如何なく発揮して登頂成功した群像劇、その軌跡だ。登攀シーンは少ないと感じた。取憑かれているとは、彼らのことだ。彼等には山しかない。切り詰めた生活をしてキャンプではズルして自分だけ腹を満たし、アウトロー達はK2に掛けた。登頂できた者、リーダーの意見を忸怩たる思いで受け入れた者、反発する者、1次隊はアテ馬と不満を持つ者。我の強さに眉を顰めながら、人生をかけたものに挑むとき「我」を張れないで言いなりでどうする!と本から声がした。2017/06/20
シガー&シュガー
15
1977年に日本山岳協会主催で行われたK2遠征の記録。著者が描きたかったのは登攀そのものではなく、遠征に参加した”はぐれもの”たちの姿だったとのこと。しかし山岳協会の主流から外れた男たちというだけで、実際は反逆色はほとんどありません。が、日本山岳界の傍流にいるしかなかった山男たちの山にかける生活のギリギリぶり、K2遠征を実現するまでの苦労、遠征中の俗臭ふんぷんたる人間模様、どれも大変に面白かったです。それにしても他人の酸素をとっちゃいけないよね…こんなこと書かれちゃったその人も山に散ってしまいました。2016/01/21
MICKE
12
大遠征隊によるK2登攀に至るドキュメント。山登りというといかにしてルートを克服するかの実地描写が主であると思ってしまうが、そのグループ内の人間模様、登るまでの資金集め等、登山するための実際のところがよく書かれている。現在のアルパインスタイルとの比較では旧態然とした手法とはなるが、ビジネスクライミングのドライな山登り、また最新技術を利用したクライミングなど、さまざまなスタイルは何が山にとって大事なのかを教えてくれる。2024/10/01
yamakujira
4
1977年のK2遠征をえがいたノンフィクション。武勇伝じゃなくて、遠征に至るまでの苦労や隊内の軋轢が赤裸々に語られ、一匹狼たちの群像劇になってるのがおもしろい。海外登山に制約の多い時代背景や、山岳界の内部事情、隊員たちの生活なども興味深い。K2登頂は偉業だと思うけれど、登山家たちの熱情は自己顕示欲と自己陶酔に由来すると暴かれて白ける一方で、かえって登山家たちの魅力が伝わる面もある。今となっては、ボンベをはじめ装備やゴミ、糞尿を放置して、ボルトやロープを残置する登山はもうやめてほしいね。 (★★★☆☆)2019/08/26
Ikuto Nagura
3
ヤマケイ文庫コーナーに本田靖春の名を見つけて購入。あとがきで本田は「正直に告白すると、書き終った私に、物足りなさが残った」と書く。社会に対する「反逆者」の姿を、登山なり登山家に見出だせると思い取材したにもかかわらず、そこに見たものは、登山という狭い世界ゆえ、より日本的な社会の縮図だったという。だけど、K2登頂成功は一人の犠牲も払わずに遂げられた。その要因は、山に懸ける人たちが、人間らしさの凝縮だったからのように私は感じた。食事についても、登頂への功名争いについても、はたまた原田に求婚する真知子についても。2016/04/20