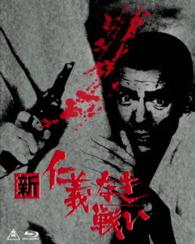内容説明
昭和十一年一月、厳冬の槍ヶ丘・北鎌尾根に消えた加藤文太郎。冬季登山の草創期、ガイド登山が一般的だった時代に、ただひとり、常人離れした行動力で冬季縦走を成し遂げていった「単独行者」は、なぜ苛烈な雪山に挑みつづけたのか。構想三十五年、加藤文太郎の真実の人間像に挑む本格山岳小説。
著者等紹介
谷甲州[タニコウシュウ]
1951年、兵庫県伊丹市生まれ。大阪工業大学土木工学科を卒業後、建設会社に勤務。その後、青年海外協力隊(ネパール)に参加。1979年、『奇想天外』誌にてデビュー。1981年、カンチェンジュンガ学術登山隊参加。カシミールヒマラヤ・クン峰登頂。冒険小説、SF小説の人気シリーズを数多く発表しつづけている。1987年「火星鉄道(マーシャン・レイルロード)一九」で第18回星雲賞短編部門受賞、1994年『終わりなき索敵』で第25回星雲賞長編部門受賞。1996年『白き嶺の男』で第15回新田次郎文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
96
2015/4/22 Amazonより届く。 2016/12/5〜12/13 新田次郎版とは違う、加藤文太郎伝。新田版を読んだ時から、自分の登山経験は増えているが、ここに書かれている行程は驚異的だ。加藤が歩いている様子を一度で良いから見てみたい。しかし、加藤さん、ほんとにこんなに口べただったんだろうか。今とは登山の立ち位置が違うとは言え、大変勿体ない気がする。下巻も楽しみ。2016/12/13
キク
64
新田次郎が「孤高の人」で描いた加藤文太郎を、谷甲州が描きなおした。山岳小説って、新田次郎と夢枕獏しか知らなかったけど、谷の描く山と加藤は凄くよかった。冬山を単独でという、登山界の常識を覆す異端はどのように生まれたのかが、丁寧に説得力をもって書かれている。実直に山と向き合う加藤が魅力的だ。僕は読書に救われて生きてきたような人間だけど、正直言うと、文豪なんかより登山家達のほうが人間として好きだ。存在証明をウダウダやってるより「それがそこにあるからだ」というスタンスで人生に向き合うほうが健全だよなぁ、絶対。2023/02/06
翔亀
50
新田次郎「孤高の人」は山岳描写の厳しい美しさと単独行者の屹立する精神により山岳小説の白眉だと思うが、それを超えるかもしれない。新田は加藤の職業訓練生時代や戦前の労働運動を創作することで加藤の悲劇性を顕わにする、谷甲州は加藤の登山だけで全てを語る。上巻では全てが加藤の遺した文章を基にしている。加藤の著作は輝きドラマ性がある(例えば1930年剱岳・剱沢小屋の雪崩遭難事件の犠牲者とその前日行動を共にしている)が、事実が淡々として述べられるだけで心情描写がなく味気ないが、加藤に成り代わって再現して見せる。2015/07/19
はるを
33
⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎。加藤文太郎というクライミングアーティストの登山列伝、武勇伝。初読み作家さんでしたが、とても読み易かったです。若さ故の不器用さと、とんがった考え方は半分は気持ちがとても理解出来て「解る、解る。そうだよね。」と思っていたが、半分は「そうじゃないでしょ?文太郎くん。」と思っていてその狭間で揺れていた自分がいた事が楽しかった。まぁ、こんなやり方やっていたらそりゃいつか遭難するよね。そんなに死に急ぐなよ、文太郎くん。劇中で出て来た山男達が意外とみんな小さい男だなぁ、と感じたのが笑えた。下巻へ。2016/11/10
saga
25
序で加藤遭難を書き起こしてくれて良かった。単独行者・加藤文太郎を最初は小説『孤高の人』で、次に自伝『単独行』で人となりを知り、最後に本書で締めくくろうと思った。他人と一緒に行動するより単独を好む彼を私は理解できる。そして、里歩きから無雪期の登山に移行し、夏山では満足できずに冬山へと突き進む様がよくトレースできた。「一月の思い出」の中において、加藤が後に遭難する一行の幻影を見た記述は何を基にしたものだろう? 単なる文章の高揚のためだとするならばいただけない……2018/01/08
-

- DVD
- 幸せです DVD-BOX 6