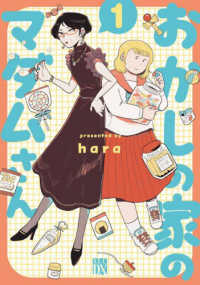出版社内容情報
本書は、16世紀後半から17世紀前半にかけて、オスマン帝国(1300年頃成立)が国制の大変革を経て「第二帝国」(Second Empire)に変貌する過程を跡づける試みである。オスマン史は一般的に、スレイマン1世(在位1520~66)の時代に「黄金期」を迎え、その後は長期的な衰退の道を辿ったと考えられてきた。こうした衰退史観に対して、本書は丹念に史料を読み込み、1622年のオスマン2世の廃位と弑逆に注目しながら帝国の変容過程を詳細に論じる。
オスマン2世は、イェニチェリ軍団の反乱により殺害された。その背景には何があったのだろうか? 本書は、その政治的要因と社会経済的背景を同時代の世界史全体の流れにも留意しながら論じた問題提起の書であり、近年におけるオスマン史研究の「転回」を象徴する好著である。とりわけオスマン帝国における制限君主制の形成と「プロト民主化」の進行は、比較の観点からも興味深い。
著者は、同時代のイギリス史や北米史とのアナロジーも交えながら、オスマン帝国なりの制限君主制への歩みを描きだした。すなわち、一方では巨大帝国の出現と市場経済化の進展がもたらした影響を丹念に跡づけつつ、他方ではスルタンへの権力集中を狙う「絶対主義陣営」と、法的制約による王権の制限を求める「立憲主義陣営」とが繰り広げる政治闘争の図式を明示することにより、社会経済的変容と政治的変動が密接に関連するものであったことを巧みに解き明かしている。
また、「立憲主義陣営」の中心勢力となったイェニチェリ軍団について、その構成員の変質を、従来の腐敗や堕落といった観点からではなく、「市民化/文民化」の大きな社会的潮流の中に位置づけた。著者によれば、イェニチェリは市場経済化の中で富を蓄えた庶民の社会的上昇経路となり、軍隊からいわば社会経済的利益集団に「進化」を遂げたのである。この「プロト民主化」により、オスマン帝国に独特の近世政治社会が形成されたのであった。
本書は、オスマン2世の弑逆事件をはじめとする多彩なエピソードを交えて、オスマン近世王権の姿を新たな視点から捉え直した。それは、いわば新興中産階級/市民が支えた新しい王権の形であった。本書で示されたオスマン的近世の姿は、西洋史研究や日本近世史研究にも接続可能であり、比較近世史・比較帝国論の観点からも大いに注目に値する意欲作である。
―
〈著者〉バーキー・テズジャン/カリフォルニア大学デイヴィス校 教授
〈訳者〉前田弘毅/東京都立大学教授、佐々木紳/成蹊大学教授
内容説明
1622年5月、若きスルタン、イェニチェリの反乱により死す―変容する政治・経済・社会のもと、オスマン帝国はいかにして歴史の第二ラウンドを迎えたのか?衰退史観を乗り越え、「第二帝国」始動のメカニズムを鮮やかに論じた問題作。
目次
序論 近世オスマン政治史
第1章 単一市場、単一通貨、単一の法―市場社会と万民法の形成
第2章 王位継承問題―法的監督のもとにおかれた王家
第3章 宮廷の逆襲―オスマン帝国における絶対主義の形成
第4章 二人目のオスマンによる新帝国建設―オスマン2世の時代(1618~22年)
第5章 絶対王政の転覆―弑逆
第6章 顕現する第二帝国―イェニチェリの時代
結論 オスマン帝国の衰退と近世
著者等紹介
テズジャン,バーキー[テズジャン,バーキー] [Tezcan,Baki]
カリフォルニア大学デイヴィス校教授。博士(中東研究、プリンストン大学)。専門分野:オスマン帝国史、イスラーム史、史学史
前田弘毅[マエダヒロタケ]
東京都立大学人文社会学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、博士(文学、東京大学)。専門分野:西アジア(イラン・グルジア)史、コーカサス地域研究
佐々木紳[ササキシン]
成蹊大学文学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、博士(文学、東京大学)。専門分野:西アジア(トルコ)史、トルコ近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
Go Extreme