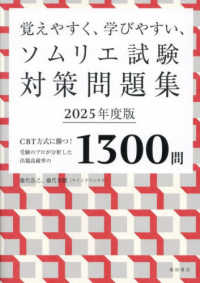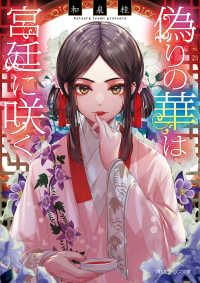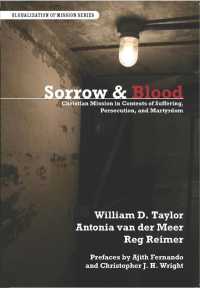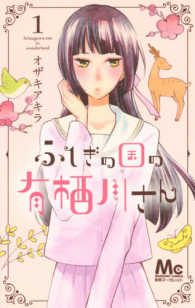内容説明
4年に一度のスポーツの祭典オリンピックは、なぜかくも多くの人々の関心を集めるのか。歴史・哲学・芸術・スポーツ科学の視点からオリンピックの意味を考える。
目次
第1章 古代オリンピック―ギリシア人の祝祭と身体(オリンピック―古代と現代;オリンピックの誕生 ほか)
第2章 精神と肉体―オリンピックの哲学(オリンピズム;哲学者・嘉納治五郎 ほか)
第3章 オリンピックと芸術―ビジュアルな古代ギリシア(オリンピアのゼウス像;オリンピック創生神話 ほか)
第4章 スポーツを科学する―身体運動の動作分析(バイオメカニズムからみるスポーツ;走る ほか)
第5章 近代オリンピックの始まり―普遍的理念とナショナリズムのせめぎ合い(オリンピックの理想と現実;近代オリンピックの発案者クーベルタン ほか)
著者等紹介
橋場弦[ハシバユズル]
1961年札幌生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、博士(文学)。現在、東京大学大学院人文社会系研究科教授
村田奈々子[ムラタナナコ]
1968年青森県生まれ。東京大学文学部西洋史学科卒、ニューヨーク大学大学院博士課程修了、PhD(歴史学)。現在、東洋大学文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
15
オリンピックを切り口とする専門横断的な試みの論集(ii頁)だが、全5章のうち3章までを古代ギリシア関連が占める。巧まずして近代オリンピックの虚構性と人為性を物語っているのでは…と要らぬことを心配してしまう。論考はどれも個性的で読み応えがある。とりわけ、芸術の中の古代オリンピックを論じた第3章(飯塚隆)。壺絵や彫刻に描かれた競技の模様は貴重な史料だが、芸術的に表現するためリアリティを犠牲にしている可能性もあり注意が必要。有名なミュロンの像と同じフォームで円盤を投げたら、記録が全く出なかったのだそうだ。2024/08/29
紙狸
5
2016年刊。ギリシャ古代史・近現代史、哲学、美学、スポーツ科学の学者たちの共著。古代のオリンピックと、19世紀後半に創設された近代オリンピックは別物なのだが、つながってもいる。最終章の「近代オリンピックの始まり」が興味深かった。近代オリンピックはあっというまにナショナリズムと結びついた。古代オリンピックのころは、そもそもギリシャという国はなかった。開催国エリスは、数ある都市国家の一つだった。第2章には、嘉納治五郎が大学で哲学を学び、功利主義に関する論文を書いていたとある。柔道だけの人ではなかったのだ。2019/08/01
真田 光
1
東大教養学部の講義を元にした、オリンピックに関わる論考集。最終章の近代五輪ができるまでとクーベルタンについてでは、「当時欧州諸国民や米国民は『イメージの中にある非実在ギリシャ』に憧れを抱き、現実のギリシャを見ていなかった」「ずっとギリシャで開催することをクーベルタンが明確に否定し、国際的な大会となるように発展させたことで、五輪は今まで生き延びた」ということが示されていて、大変興味深い。2016/12/14
こ~じぃ。。
0
柔道の父 嘉納治五郎さんって哲学者でもあったんだ・・・2016/09/14
Ikkoku-Kan Is Forever..!!
0
知ってるようで知らないことが多いな。2020/01/04