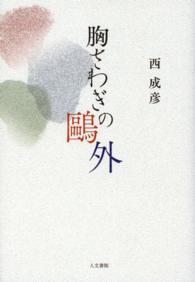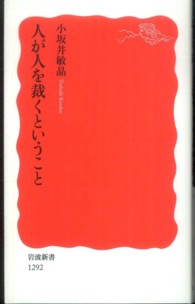内容説明
聖俗が融合し、神秘と幻惑に満ちた劇場都市イタリアはバロック美術の壮大なラビリンス。その華麗な美と魅力を訪ねる。
目次
第1章 バロックの土壌(バロックとは何か;カトリック改革のローマ;聖年という装置 ほか)
第2章 ローマ・バロックの展開(カラヴァッジョの革新;アンニーバレ・カラッチとボローニャ派;ベルニーニの劇場 ほか)
第3章 バロックの港(ナポリ;ジェノヴァ;ヴェネツィア ほか)
著者等紹介
宮下規久朗[ミヤシタキクロウ]
1963年名古屋市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業、同大学院人文科学研究科修了。神戸大学文学部助教授。主要著書・訳書:『ティエポロ』(トレヴィル1996)、『バロック美術の成立』(山川出版社2003)、『カラヴァッジョ―聖性とヴィジョン』(名古屋大学出版会2004、地中海学会ヘレンド賞・サントリー学芸賞受賞)、など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
317
タイトル通りのイタリア・バロックの概説書ではあるのだが、写真の安っぽさといい、なんだかガイドブックのようだ。実際、この本の有用性を考えるならば、まさにガイドブックが最適であるのかも知れない。あるいは山川出版社の刊ということからすれば初級の教科書か。全体の半分近くをローマがしめるのだが、さもありなんローマは有数のバロック都市でもあるのだから。建築でいえばボロミーニにコルトーナ等、美術ではなんといってもカラヴァッジオにベルニーニが。その他にもサン=ピエトロの内部空間といい、ローマはまさにバロックの宝庫である。2022/10/17
OKKO (o▽n)v 終活中
6
図書館 ◆バロック建築、特にファサードを求めて三千里。これは宮下先生が記したガイドブックとでも申せましょうか。写真を求めるなら本書は選ばないほうがよいが、取り上げた事例に「さすがだ」とうなる ◆あんまりがっつり読めなかったが、また必要なときに参照しよう2017/06/08
MIE
4
ローマに行きたくなった。これは旅行の時に持っていくのがいいですね。次にローマに行くときはカラバッジョが見たい。あとボルゲーゼ美術館にももう一度行きたい。他にもたくさん行きたいところがありすぎて、いつも時間が全然足りない。2015/04/26
Zeynep
2
古代遺跡だけではなく、ローマにはバロックの素晴らしい町並みもあります!でもバロックでなんですか?というバロック初心者が手にした一冊。 とりあえずカラバッジョとベルニーニとボロミーニはおさえておこう。2015/10/31
ねむねむ
1
図書館で借りて読んでみて気に入ったので、購入しました。 イタリア旅行に持っていきます。2013/08/08