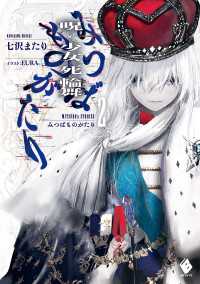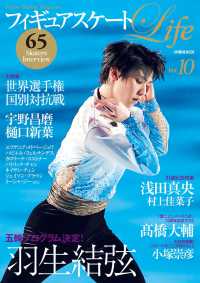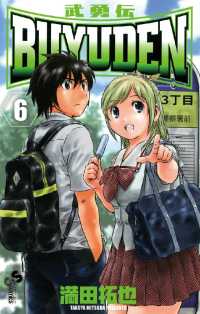内容説明
本書は、一九九五年十一月十二日に東京大学でひらかれた第九三回史学会大会・日本史部会(近世)におけるシンポジウム「社会的権力」の内容をベースとして新たに編集したものである。
目次
社会的権力論ノート
幕末期松本藩組会所と大庄屋・「惣代庄屋」
岡山藩における村役人選任をめぐって
近世領主支配と村役人・郷宿・下級役人
江戸における関八州豪商の町屋敷集積の方針と意識―関宿干鰯問屋喜多村寿富著「家訓永続記」を素材に
大坂本両替仲間の組織と機能―御用と商売をめぐって
近世中後期における芸能興行と売薬渡世
西国の侠客と地域社会―豊後国杵築の「粋方」を中心として
「中間支配機構」を「社会的権力」論で読み直す―惣代庄屋と大庄屋の「間」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Cebecibaşı
1
江戸期の民衆世界と政府権力世界を仲立ちする中間集団に関する論集。中間集団が他の2集団の間で立ち回りながらかれらに匹敵する権力主体としてヘゲモニーを獲得し、社会が構成されていたとする。それは庄屋層であったり目明し層であったり様々であるが、地域社会論と組み合わせることで地域社会における権力構造が見えると同時に「地域」の輪郭もよりはっきりと浮かびあがる。他地域の研究にも応用できそうな理論的枠組みだと思う。永田雄三がアーヤーンとジェントリと郷紳の比較を展望していたが、社会的権力論にヒントがあると思う。2020/02/17