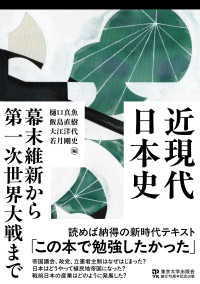内容説明
歴史研究は社会にとってどのような意味をもつのか。重野安繹と久米邦武は、日本の近代歴史学の草創期を担った歴史家である。しかし、彼らが歴史家となった経緯は、後の時代の歴史学者とはまったく異なっている。そして彼らに求められたのは、明治政府の官吏として、国家の「正史」を執筆することであった。彼らの栄光と挫折の軌跡を追うことは、社会にとっての歴史研究の意味という問いを改めて考えることでもある。
目次
歴史家の誕生
1 藩と江戸(幕末の経歴;昌平黌と重野 ほか)
2 西洋との出会い(薩英戦争と情報収集活動;ふたたび学者として ほか)
3 「抹殺論」の時代(明治政府の修史事業;川田剛の追放と「大日本編年史」 ほか)
4 修史事業の終焉(久米事件;修史事業の修焉 ほか)
著者等紹介
松沢裕作[マツザワユウサク]
1976年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程中途退学。専攻、日本近代史。現在、専修大学経済学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュンジュン
8
正史とは国家が編纂した歴史書の事。正統性をアピールしたい明治政府によって、その任務は2人に託された。以前の時代なら生涯をかけて成し遂げられただろう。だが、時は文明開化、否応なく近代歴史学の洗礼を浴びる。旧き正史を新しき方法で書く、二つの潮流の激突に翻弄される二人。結果、未完。二人を通じて、難産となった”歴史家”誕生の瞬間に立ち会う。2024/03/05
africo
3
日本の近代歴史学の揺籃期に国策としての史書編纂に携わった2人の歴史家の評伝。リードした2人の功績(実証の萌芽)や歴史哲学は興味深いものの、ブックレット形式のページ数の少ない本の中でしかも2人扱っているので物足りなさは否めない。しかし、元々2人とも漢学者で、職務として歴史に携わるうちに歴史の重要性を認識していったのみで、そもそも歴史を志した訳ではないという状況、そこで初めて近代歴史学が産まれたという状況は、表向き歴史を誇ったフリをしつつ実際のところ歴史を軽視しているこの国の体質を端的に表している気がする。2021/09/11
G.Brothers
3
久米邦武と言えば東京大学資料編纂室を作った人である。そこに現代フーコー研究者の意見、ドキュメントなどの概念をぶっこんでみたい。結果から申して意地悪だが、歴史が得意な人って資料編纂に向いてないだろうか?2020/11/16
カラス
2
明治初期の二人の歴史家を対比的に取りあげた本。どちらか一人ではなく二人を扱ったおかげで、テーマが鮮明にでて分かり易くなっていたように思う。二人にとって歴史研究は官吏としての業務であり、だからこそ歴史は何の役に立つかということを世間に説明する責任を負わせることになってしまったという著者の説明が心に残った。「歴史は何の役に立つか?」という問いは素朴かも知れないが普遍的なテーマであり、重野と久米のそれぞれの「説明」はあまり納得のいくものではないものの、どうにかしてそれを説明しようとするその姿勢には好感を持った。2019/06/14
トリタニ
2
彼らの史観には好感が持てる。ただ、歴史家は公平であるべきだ、というのは納得できるが、簡単に実行できることではないと思う。2014/04/22
-
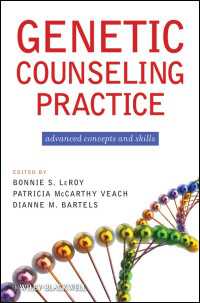
- 洋書電子書籍
- Genetic Counseling …