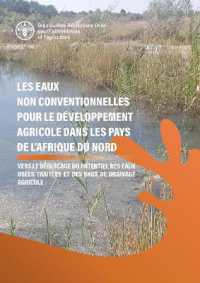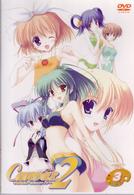内容説明
徳川家康は、戦国の争乱から天下泰平にいたる時代をいかに生きたのか。家康といえば、江戸時代に「神君」とする流れのなかでつくりあげられた家康神話や、また忍従・冷酷・策士・狡猾といったイメージがあるだろう。後世につくられたこうした家康像から脱却するために、本書では古文書・古記録などの一次史料に基づき、長い生涯の時々におかれた政治的位置や社会的位置に視点をおいて、その実像を描く。
目次
七四年を生きた家康
1 人質から客将へ―そして離反・独立
2 戦国大名から織田大名へ
3 主をもたぬ大名―羽柴秀吉との攻防
4 豊臣最有力大名―「関東之儀」を扱う
5 豊臣政権の大老―外様大名から大老へ
6 天下人家康―大老を越えて
7 大御所―実権の具体像と秀忠への権力移譲
著者等紹介
藤井讓治[フジイジョウジ]
1947年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。専攻、日本近世史。現在、京都大学名誉教授、京都大学博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新田新一
17
歴史が好きなので、山川出版から出ている歴史リブレットのシリーズを読むのが楽しくてたまりません。客観的な記述の中にかえって歴史のロマンを感じます。本書は小説やドラマでお馴染みの徳川家康の生涯を描いたものです。秀吉の配下にあると思っていた家康が、機を見て天下を取ろうとしたことが分かります。このことから、歴史は固定的なものではなく、絶えず揺れ動いていることを理解できました。固定的な歴史の見方は、教科書的な知識から来るようです。この本は結末が特に印象的です。ここを読むと、天下人としての家康の感慨が心に染みます。2024/05/04
田中峰和
5
74年を生きた家康の生涯が7分割して紹介される。その1は人質から客将へ、2は戦国大名から織田大名へ、3は羽柴秀吉との攻防、4は豊臣最有力大名、5は豊臣政権の大老、6は天下人家康、7は大御所。妻の築山殿と嫡男の信康、娘婿の秀頼を殺害したことが、冷酷というイメージにつながるし、関ケ原の戦いで小早川の寝返り策謀、方広寺鍾銘事件は策士・狡猾のイメージとなる。明治政府は、さらに朝廷の抑圧者としてイメージを悪化させたが、戦後の高度成長期には企業経営の視点から優れた組織者として見直された。将来的にはどう評価されるのか。2021/11/02
相米信者
5
関ヶ原の戦いで勝利し、江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康のコンパクトな評伝。織豊政権下の家康の動向や、二代将軍・秀忠にどのように権力移譲したのかが見事に描かれている。同著である『徳川家康』(人物叢書)も一読してみたい。2021/05/05
としき
2
徳川家康と言えば山岡荘八先生の歴史小説のインパクトが強く、史実には基づいているが歴史上の人物に感情導入がされているので、偏った思い込みが強くなる。この本は歴史の教科書でも有名な山川出版社が発行元になっているので、あくまでも知りうる史実に乗っ取って書かれているので、歴史の勉強にも大変役に立つ。特に残る文献から信長と家康、秀吉と家康の上下関係などは歴史の変遷と共、移り変わる様子がよくわかる。また秀忠に権限を移行していく様子から、なぜ徳川政権が永きに渡ったことも垣間見ることが出来て、楽しく読み切ることが出来た。2021/06/24
TOM
1
家康の人物像は近世の編纂物により作られ、それが小説やドラマによって我々に刷り込まれてきた。本書は一次史料によることで、コンパクトかつ学究的に等身大の家康に近づこうと試みるものである。 本書で重点的に述べられているのは、家康の"立ち位置"である。今川の"人質"という立場、織田信長との"同盟関係"という立場、信長亡き後に秀吉の属下に入るという立場、秀忠に将軍職禅譲後の大御所としての立場、これらが果たして従来の見解でふさわしいのか、文書形式に目を配ることによって、我々の凝り固まった家康像に注意を促す。2022/12/29