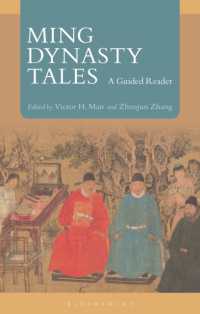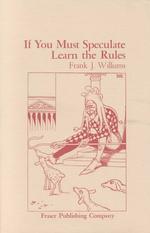内容説明
武士が尚ばれた時代、「八幡太郎」と呼ばれて親しまれ、神のように仰がれた源義家。彼と同時代を生きたある貴族は、その日記に、義家を「天下第一の武勇の士」「武威は天下に満ち、誠にこれ大将軍に足る者なり」と称讃する一方、「多く罪なき人を殺す…積悪の余、ついに子孫に及ぶか」とも記している。「文武兼備の稀代の名将」と「残虐を事とした暴力装置」という対照的な評価のあいだで揺れ動く源義家の実像に迫る。
目次
源義家のイメージと実像
1 父祖の功業
2 義家の登場
3 延久年間における陸奥の賊徒追討
4 河内源氏と鎌倉
5 後三年合戦
6 坂東との関係
7 白河院と河内源氏、その空間
8 義家の評価
著者等紹介
野口実[ノグチミノル]
1951年生まれ。青山学院大学大学院文学研究科史学専攻博士課程修了。文学博士。専攻は日本中世史。現在、京都女子大学宗教・文化研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mijas
39
源義家が「八幡太郎」と呼ばれ、文武共に兼ね備えた風雅な武将というイメージはなぜ作られたのかという問題設定。源義家が詠んだとされる「吹く風をなこその関と思へども道もせにちる山桜かな」も実際は作者不明の歌だとのこと。源義家像は後世になってデフォルメされたもののようだ。「梁塵秘抄」にある今様「八幡太郎はおそろしや」が紹介され、源義家の実像に迫っている。その他、文献を引用しながらの詳しい検証がされている。山川出版のこのシリーズ「日本史リブレット 人」は色々な人物を取り上げている。学術的なので日本史学習に良い。2017/07/26
けんけんだ
12
東京都杉並区にある大宮八幡宮は、平安時代に源頼義、義家が奥州遠征時に勝利祈願等を祀るために創建した長い歴史を感じる神社です。参道に義家の鞍掛の松があったりします。義家に関する本を探して読みました。歴史は面白い。八幡太郎義家像も「天下第一の武勇の士」と残忍な殺戮を繰り返す「武士の長者」という2つの顔があるそうです。2021/09/12
金目
3
平成の発刊なので、人物叢書よりは大分批判的に纏められている。伝説的な説話を概ね虚構と断じ、歴史的評価を「栄光の大将軍」と残忍な「武士の長者」の2つに集約している2024/11/02
葉つき みかん
2
義家は白河院と仲が悪いかと思っていたけれど、実は白河院に重用されていて、白河院の御所・六条辺に邸宅を構えていたらしい。七条が平安末期には金属加工の中心地で、武士の必需品である武具を生産していた事も初めて知りました。鎌倉幕府草創の頃は、源氏の武芸故実の祖は頼義とされていたが、それが義家に移行した理由①北条時政が自分を義家の外祖父・平直方になぞらえていたから②室町幕府を開いた足利氏が義家流だったから、というのが興味深かった。2013/02/21
カラス
1
義家に興味があったので読んでみたんだけど、ちょっとわかりにくい本だった。前九年と後三年はわかりにくい出来事なので(特に人間関係)、仕方ない部分はあるけれど、もうちょっとこう何とかならなかったんだろうか。できれば、義家がどんな人間だったかに絞ってスマートに書いて欲しかった。ただ、保元・平治以前の武士を概観する本としてはまあまあよかった。頼朝につながる源氏の物語を、あるていど見渡すことができる。2018/01/21