内容説明
律令国家体制の確立を担った二人の君主、天武と持統は、中国で唐王朝が成立し、朝鮮三国の抗争が新羅による統一で決着する東アジアの激動期に、卓越した指導力を発揮して、機構による支配への道を切り開いた。白村江での敗戦、壬申の乱勝利という大きな戦いの影を引きずりながら、律令編纂、官人制の樹立、都城の形成、さらに「天皇」号の確立、「日本」国号の制定へと、新しい国家の形をつくりあげた夫妻の足跡を、時代のなかに位置づけ、たどっていく。
目次
大君は神にしませば
1 壬申の乱と軍国体制(大海人の立場;壬申の乱 ほか)
2 律令編纂と支配体制(近江令から大宝律令まで;氏の再編 ほか)
3 飛鳥の宮から藤原京へ(重層する飛鳥「岡本」の宮;酒船石遺跡と石神遺跡 ほか)
4 王位継承方式の模索(群臣推戴と先帝遺詔;吉野誓盟から持統の権力掌握まで ほか)
歴史書の編纂と国際認識
著者等紹介
義江明子[ヨシエアキコ]
1943年生まれ。東京都立大学人文科学研究科。専攻は日本古代史、女性史。現在、帝京大学名誉教授主要著書(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
98
天武天皇と持統天皇の政策をまとめた本。専門的な記述が多くて、読むのに苦労した。こういった本を読むと、高校で習った日本史は歴史のごく表面だけを取り扱ったものであることが分かる。淡々とした学術的な文章だが、豪族の集合体であった大和朝廷が律令国家として生まれ変わる、ダイナミックな歴史の転換点を感じ取れる内容。「春過ぎて夏来るらし白布の衣乾したり天の香具山」の作者持統天皇は、したたかな政治家だったことが分かったのが一番面白かった。2014/09/12
むむむ
2
薄い本だけど読み応えは十分。天武即位前から持統の死までを解説。奈良時代の話も。天武持統の時代って短いけれどその間に現在にも続く日本のイメージや伝統も作られていったようだ。王位継承方式が模索されるんだけど、その根底にあるのが推古天皇だった。今回一番驚いたのは推古の存在の大きさかもしれない...もちろん本書のテーマではないけれども...やっぱりこの時代が好きです。2019/04/24
takuchan
2
理想の夫婦!叔父と姪の関係でもありますが^^;持統は壬申の乱時には桑名におり顕著な活躍をしておらず、吉野や伊勢へのの行幸で壬申の乱を天武とともに先頭に立って戦い抜いたかのようか自画像をつくりだしていたという記述が一番印象に残った。 /白村江での敗戦、壬申の乱勝利という大きな影を引きずりながら、律令編纂、官人制の樹立、都城の形成、天皇号の確立、日本号の制定と、新しい国家の形をつくりあげた夫婦の足跡2015/01/25
kayopon
1
まさかこんな固〜い感じの本だとは思わず…。教科書の補助教材のようでした…。 でも改めて天武天皇と持統天皇の偉業や、カリスマ性を知ることができました。宝塚好きの私は、大海人皇子と額田王が主人公の「あかねさす紫の花」が大好きだったけど、あの時チラッと出てきてた鸕野皇女が持統天皇だったのねー‼️と今更ながらに知りました?お恥ずかしい…。2018/05/06
dolce-vita
0
天武天皇と持統天皇の大ファンです。実際に明日香や関ヶ原を訪れて歩いた史跡の地理やその意味、今まで読んだ本や小説の内容をきちんと整理する意味でもとても楽しめた。表紙の飛鳥浄御原宮の復元模型を見るだけでも大興奮♪天武天皇のカリスマ性と持統天皇の政治手腕。この二人がつくりあげた中央集権の律令国家。それがつくられていく過程は本当にわくわくする。2016/12/10
-

- 電子書籍
- 征服王の愛玩妃【タテスク】 第21話 …
-

- 電子書籍
- いじめ探偵【単話】(32) やわらかス…
-
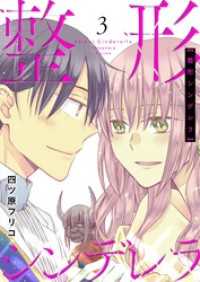
- 電子書籍
- 整形シンデレラ【描き下ろしおまけ付き特…
-
![まんが4コマぱれっと 2020年2月号[雑誌] 4コマKINGSぱれっとコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0805965.jpg)
- 電子書籍
- まんが4コマぱれっと 2020年2月号…





