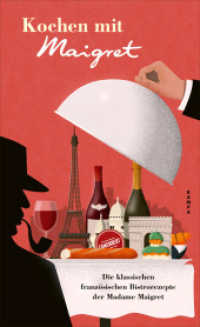内容説明
江戸時代は、問屋・仲買といった商人同士が特定の商品を大量に取引する専門的な市場が、各地に登場した時代だった。蝦夷地から九州まで、全国各地で生産され、遠くまで運ばれ消費される魚肥を例に、江戸や東浦賀、大坂といった中継拠点の都市に誕生した市場のありさまをさぐり、商人と流通の歴史を考える。
目次
市場とはなにか
1 干鰯場の誕生
2 問屋と仲買
3 大坂の干鰯屋仲間と市場
4 重層する市場
5 流通の変動と市場
著者等紹介
原直史[ハラナオフミ]
1962年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。専攻、日本近世史。現在、新潟大学人文社会・教育科学系(人文学部)教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鯖
18
江戸や東浦賀、大坂といった中継拠点の都市に誕生した市場を魚肥と通じて俯瞰する本。干鰯って九十九里の鰯ばっかりだと思ってたら、蝦夷地の鰊等全国各地にあるんだなあ。俵を1つ出してそれで値付けをしたら、他のものは全然レベルが低くて文句ついたり、市場の外に干鰯を積んだ船が浮いててそこで保管したり。やっぱり臭いの問題なんじゃろか。そこは触れられてなかったけど。2025/06/28
ずしょのかみ
4
魚肥流通における近世の市場構造を解明した。 林玲子は、木綿問屋の検討を通じて売買受諾の口銭を収入源とする荷受問屋から、自己資金による売買差額を収入源とする仕入問屋への移行を明らかにし、両者を一連の存在とした。一方で、塚田孝、桜井英治らは荷受問屋と仕入問屋を、成立を異にする別系統の存在として捉えている。本書は後者の問屋の性格を実証した。 問屋の性格は、江戸大坂を中心に、特定の商品流通から論じられてきた。地方の市場・流通構造や流通商品を総体として捉えたばあいどのような結果になるか。気になる。2019/12/20
見もの・読みもの日記
1
江戸と大坂の干鰯(ほしか)=魚肥市場の成立と運営の様子を描き出す。肥料なんて栄養があればいいのかと思ったら、土地や作物によって合うものが異なる、複雑で繊細な商品であることを初めて知った。2017/09/04