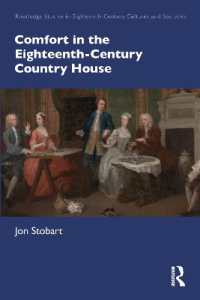内容説明
ナチ・オリンピックと呼ばれたベルリン五輪。ボイコットを余儀なくされたモスクワ五輪。天皇杯の下賜。スポーツによる思想善導政策。戦時下における外来スポーツへの弾圧。スポーツと政治の密接な関係を示すこうした事例をひとつひとつ掘り下げながら、それらを歴史的な文脈のなかでとらえる。それは、単なるスポーツと政治の関係を把握にとどまらず、スポーツを介しながら、私たちを近代天皇制や国民統合、ファシズム、戦争といった日本の近現代史のいくつかの重要なテーマへと導いていくはずである。
目次
スポーツと政治のデリケートな関係
1 天皇杯の誕生―新しい皇室像とスポーツ
2 「スポーツ狂時代」の国家戦略
3 ナチ・オリンピック―第二次大戦への跳躍台?
4 戦時下のメディアとスポーツ
5 「冷戦」の時代とその終焉
著者等紹介
坂上康博[サカウエヤスヒロ]
1959年大阪生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程満期退学。専攻、スポーツ史、スポーツ文化論、社会史。現在、福島大学行政社会学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
14
タイトルは漠然としているが、内容はほぼ日本の事例のみ(ほとんどが戦前)。昭和天皇が即位前からスポーツの庇護者として演出され、天皇杯の前身である東宮杯まで制定していたとは知らなかった。最初期の「開かれた皇室」イメージを流布する上で、スポーツは使い勝手がよかったのだろう。また、当時の政府は「思想善導」(左翼対策)の切り札としてもスポーツに期待していた。健全な肉体は共産主義を寄せつけないという思い込みによるものだが、後に東側諸国がスポーツを恰好の宣伝材料としたことを考えるとこの上ない皮肉である。2024/08/18
gecko
10
スポーツと政治の関係を示す、1920年代以降の事例を歴史的な文脈の中でとらえる一冊。若き皇族によるテニス、ゴルフ、登山、スキーなどへの情熱の披露は、スポーツを媒介として国民に「新しい皇室像」をアピールするものであった。また、健康な心身を育むスポーツは、国民の思想を堅実に導き、不平や鬱憤を忘却させるものとも考えられた(「思想善導」政策)。しかし、特定のスポーツ観を人々に内面化させる企てはあまり成果をあげず、戦時下においても、軍事色を強める学校生活とラジオで野球や相撲を楽しむ生活が並存した時期もあったという。2021/10/13
t78h1
2
スポーツによって天皇をどのように国民に馴染ませ、また親近感をわかせながら「神聖なもの」としてどう線引きしていったかなど分かりやすく書かれている。短いがスポーツと政治の関わりを知る上で優れていてる。2013/02/11
Youhei Hatakeyama
1
1番印象深かったのはモスクワボイコット。有名な話だが、その構造を全く知らずにここまで来てた。今同じようなことが起きたとき、果たしてあの時と別な行動がとれるだろうか?たぶん無理だろうな。2018/02/11
ファイター
0
スポーツを普及させることで、政府は国民の思想を善導したり、鬱憤を発散させたりすることができる。(過度の)愛国主義を植え付けることも可能。 戦前の日本政府はこれを行ったし、それが戦争につながったと思われる。 ということを書いた本。読みやすい。2015/11/16
-

- 洋書電子書籍
- A Companion to Nord…