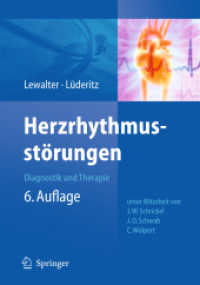内容説明
工部省が存在した明治三年から十八年までの明治前期、太政官時代は近代日本の統一国家としての政治・行政、さらには資本主義や科学技術の枠組みの生成期であった。そのなかで工部省は、西洋から導入した新技術を用いて大規模事業を経営する役割を負っていた。先進国から技術を導入して日本に適用し、お雇い外国人を雇用してその知識を求める一方で彼らの権限を制限すべく努力し、それに代わる人材を養成する、あるいは外国人経営と対抗するなど、万国と対峙する役割は明治政府そのものの課題であった。そしてその事業の一部が意味を失い、また一つの省として存続してゆくことの意味もなくなっていった過程は、近代日本の行政、産業、技術などをめぐる枠組みが整っていく過程を裏面から示している。工部省は明治前期の諸課題とそれへの政府の対応を象徴的に示す官庁であり、その検討はこの時期のこの国のありようについて様々な知見を与えてくれるであろう。
目次
1章 工部省の一五年
2章 官営事業の財源確保
3章 工部省の技術者養成―電信の事例を中心として
4章 英国からの視線―『エンジニア』誌に見る明治日本の技術事情
5章 鉄道技術者集団の形成と工部大学校
6章 日本近代化手法をめぐる相克―内務省と工部省
7章 製鉄事業の挫折
8章 官営鉱山と貨幣原料
9章 工部省の廃省と逓信省の設立―明治前期通信事業の近代化をめぐって
10章 佐佐木高行と工部省
著者等紹介
鈴木淳[スズキジュン]
1962年生。現在、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。