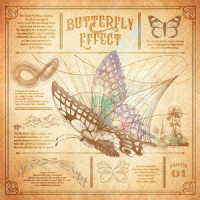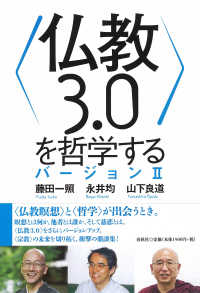目次
第1章 ロシア統治下のイスラーム(ロシアの中のムスリム地域;征服と服従 ほか)
第2章 ソ連時代のイスラーム(ロシア二月革命から自治宣言へ;ソヴィエト政権とイスラーム ほか)
第3章 イスラームの覚醒と再生(革新派の出現;ヒンドゥースターニーの反論 ほか)
第4章 イスラームの政治化と過激化(イスラーム復興党の試み;ウズベキスタンの動向 ほか)
著者等紹介
小松久男[コマツヒサオ]
1951年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専攻、中央アジア近現代史・中央アジア地域研究。現在、東京外国語大学大学院総合国際学研究院特任教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。