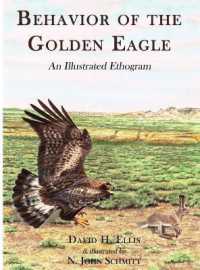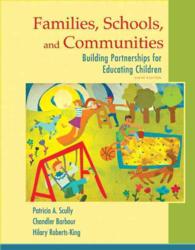内容説明
世界史上、都市は多様な人々とモノの交流する空間として存在し、それぞれの文明圏において独自の歴史的役割を演じてきた。本書は、中世ヨーロッパ世界で生まれた都市のイメージと特質をさまざまな角度からとらえ、中世都市とは何であったかを明らかにすることで、現代世界の「都市問題」を考え直す糸口を探る。
目次
都市イメージの再考
中世都市の生成
中世都市のコスモロジー
中世の都市空間
中世都市生活の枠組みと人的絆
中世末期の都市と社会
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
組織液
14
今まで読んできた阿部謹也の本などにもある内容だったので、あまり新しい知識などは得られませんでしたが復習にはなりました。「ヘンリー7世が自国の病院建設のためにフィレンツェの病院を視察し、モデルにした」というのは初耳でしたね。これヘンリー7世本人がってことなんでしょうか?リブレットの『中世ヨーロッパの農村世界』も読んでみます。2021/02/15
海星梨
6
リブレットで勉強した気になろうキャンペーン。家族単位は核家族から多核家族まで様々であった。女性も労働力として重要で、織物や服飾のギルドでは親方になれたほか、寡婦となった時に亡くなった夫から親方を引き継げる職種もあった。宗教的な兄弟団に一定の会費を払って所属し、疑似家族を形成していた。学生・教師のギルドから大学が誕生。キリスト教の理念から始まった施療院は、富裕市民の寄進や、ギルド内の扶助でも立つようになり、救済内容も細分化していった。あんまり詳細な記述はなくて想像力は掻き立てらせず。2024/04/08
†漆黒ノ堕天使むきめい†
5
ハンザ同盟やメディチ家など中世ヨーロッパを学ぶ上で聴いたことがある名前が出てくる。そのためこの頃の時代に興味を持った人や、世界史を学んでいる(学ぶ)人に薦めたい。 実際世界史を高校で学んでいた頃よりは細かく知ることが出来たと感じている。 例えば、病人や貧者を助けるためのシステムがあったことは私は知らなかった。またこの時代の商業は名詞としては習いつつ、関係性をしっかり理解できていなかったのだと気づくことが出来た。2015/08/08
サアベドラ
4
中世ヨーロッパ都市の入門・概説書。手堅い内容。著者は中世ネーデルラントおよびフランドルの都市史が専門。そのものずばり『ブリュージュ』(中公新書)なんて本を書いてたりする。現在は首都大の教授。同じ中世西欧のはずなのに、自分が専門としている地域とは色々なものが違いすぎてて泣ける。うちのところは都市どころか町や村すら存在しない極端な土地なので、比較するのもアレなのですが。2012/12/27
ももいろ☆モンゴリラン
2
多様な機能を持ち合わせた都市世界を、そも誰が企図したのだろう。聖職者と限られたもののみ城郭内に住んでいた時代から、商工者、大学、養護施設に至るまで、都市は破壊と拡充を繰り返しながら成長する。それでも日本の人口に比すると欧州のそれはなんだか少なく見えちゃうのって、こちらが許容量をとっくにオーバーしてるからだったりして。2025/09/22