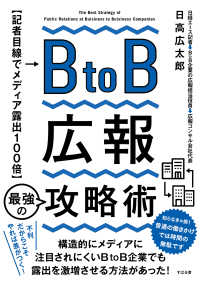- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
古代の相撲節会につながりを持ち、江戸時代、経済が発展する中で庶民の娯楽として軌道にのった相撲興行。相撲渡世集団がいかに柔軟に、創造的に社会の変化を吸収し現在まで存続してきたか、その歴史を追う。
内容説明
古代の相撲節会につながりを持ち、江戸時代に庶民の娯楽となった相撲。常に社会に応える創造と工夫があってこそ、現在の大相撲が存在する。相撲はどのように日本の伝統文化に育ったか。伝統文化の本質を歴史のなかに探る。
目次
序章 江戸の相撲―伝統文化の原型
第1章 古代と中世の相撲
第2章 武家の相撲から勧進相撲へ
第3章 四季勧進相撲の確立
第4章 軌道に乗る四季勧進相撲
第5章 大名抱えと相撲取の身分
第6章 相撲渡世集団と地方
終章 明治から現在へ―天覧相撲のあゆみ
著者等紹介
高埜利彦[タカノトシヒコ]
1947年生まれ。1974年、東京大学大学院人文科学研究科修士課程中退。学習院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
4
「日本書紀」に記述の野見宿禰と當麻蹶速による争いが相撲の始まり。その後停滞していた相撲は、近世の織田信長によって大きく飛躍した。信長は大の相撲好きで安土に千五百人の相撲取りを集めたとされる。優秀者には太刀や脇差のほか、百石と私宅まで与えた。仏教と同様、相撲の枠組みも江戸時代に形成された。本山が末寺を編成し、末寺の抱える檀家の財政支援を前提に、組織全体が成り立っている。その枠組みは華道や茶道などの家元制度にもみられる。このような枠組みの形成が相撲にも存在する。スポーツではなく国技と呼ばれる所以である。2022/10/18
転天堂
0
あまり詳しくなかった江戸時代の親方・興行について大変勉強になった。2022/05/16