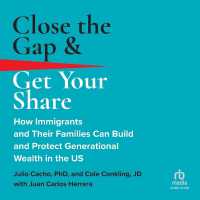内容説明
ともに独自の世界通史に挑戦した、気鋭の中国史家とオスマン帝国史の泰斗が「歴史の常識」を根底から問う!ユーラシア史からみると日本史は「意味不明」?グローバル・ヒストリーは本当に「グローバル」?中国が強調する「中華民族」は実在するのか?etc..歴史を見直し、現代世界を捉え直すヒントに満ちた1冊!
目次
プロローグ 歴史とはなにか―その「自明性」を問う
第1章 「文明」と「世界史」を考える
第2章 「世界」の捉え方―東西、華夷
第3章 統合とアイデンティティ
第4章 「宗教」を考える
第5章 「支配」のあり方
第6章 環境・文化・社会のあり方―地理的・生態的環境と社会関係
第7章 国家・国民・民族を考える
エピローグ 中国、そして日本
著者等紹介
鈴木董[スズキタダシ]
1947年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。法学博士。専攻はオスマン帝国史だが比較史・比較文化にも深い関心を持つ。83年より東京大学東洋文化研究所助教授、91年より同教授、2012年より東京大学名誉教授。トルコ歴史学協会名誉会員
岡本隆司[オカモトタカシ]
1965年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(文学)。京都府立大学教授。専攻は東洋史・近代アジア史。『近代中国と海関』『属国と自主のあいだ』(ともに名古屋大学出版会。前著で大平正芳記念賞、後著でサントリー学芸賞受賞)、『中国の誕生』(名古屋大学出版会。アジア・太平洋賞特別賞・樫山純三賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
ta_chanko
かんがく
ピオリーヌ
不純文學交遊録