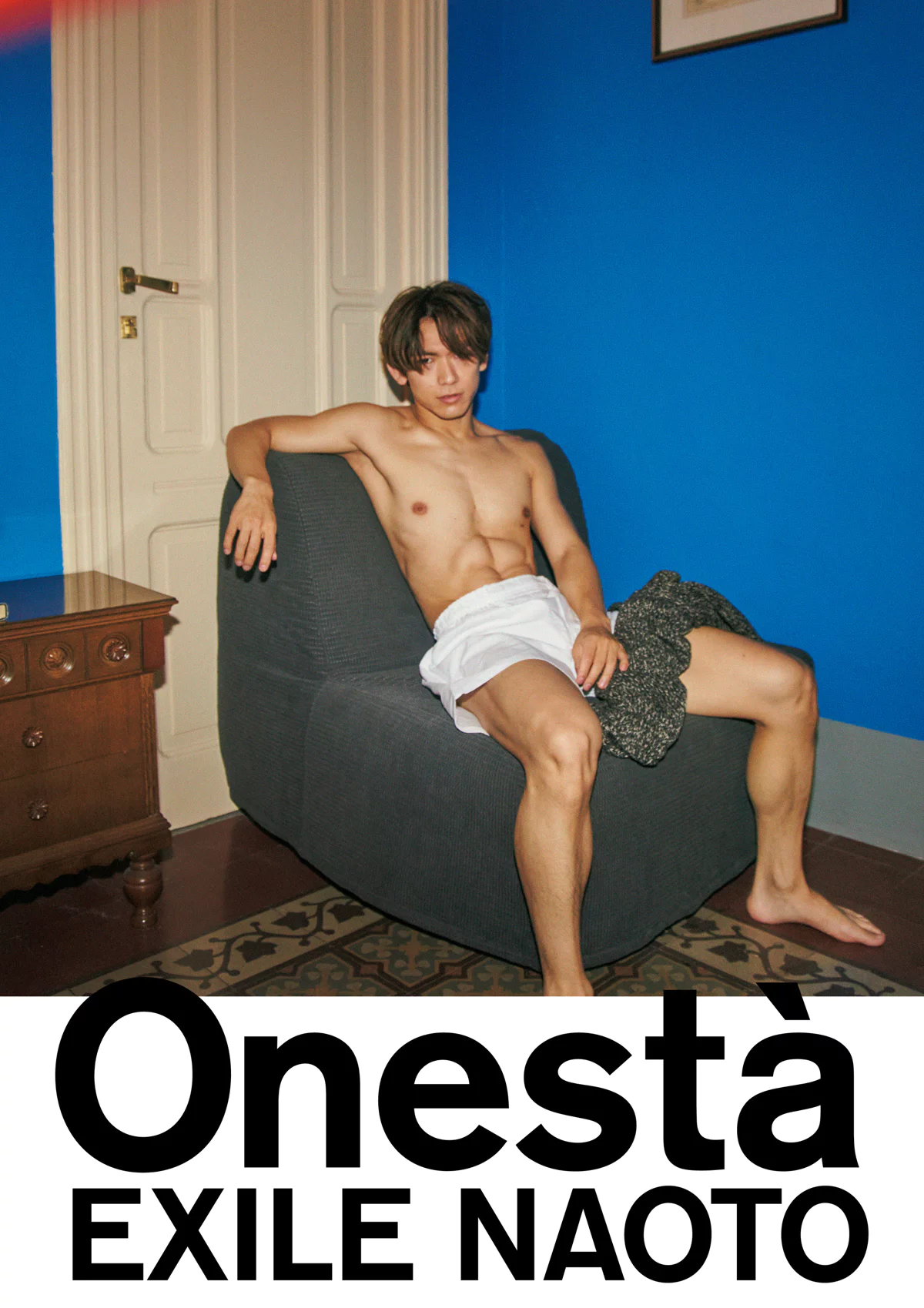出版社内容情報
日本語のオリジナルな用例を掲げた、理想の語用論入門テキスト。タスク・練習問題・ヒントで理解を深め、発話の目的を明らかにする。
序章 本書を始めるに当たって
0.1 語用論とコミュニケーション理論
0.2 コミュニケーション理論の普遍性と用例の個別性
0.3 本書の構成と新版のコンセプト
第1章 語用論の基礎
1.1 文の意味と発話の意味
1.2 発話の効力を決定する発話状況
1.3 発話状況によって決定される効力
1.4 語用論と他領域とのアプローチの違い
1.5 語用論の諸問題
1.6 日本語教育における語用論
第2章 協調の原理
2.1 会話がかみ合うとはどういうことか
2.2 グライスの協調の原理
2.2.1 会話における協調性
2.2.2 四つの下位原則
2.3 会話の推意
第3章 関連性理論
3.1 関連性理論の出発
3.2 関連性
3.3 推意と表意
3.4 処理労力と呼び出し可能性
3.6 高次表意
3.7 関連性理論からみた配慮表現
第4章 発話行為論
4.0 発話行為論とは何か
4.1 行為の理論としての発話行為論の概観
4.2 オースティンの発話行為論
4.2.1 遂行文と遂行動詞
4.2.2 発語行為、発語内行為、発語媒介行為
4.3 サールの発話行為論
4.3.1 オースティンからサールへの発展
4.3.2 適切性条件
4.3.3 サールの発語内行為の五分類
4.3.4 発語内目的
4.3.5 適合方向
4.3.6 表現される心理状態
第5章 発話機能論
5.0 発話機能とは何か
5.1 発話機能論の歴史
5.2 ハリデーの機能文法における発話機能
5.3 サールの発話行為とハリデーの発話機能の比較
5.4 山岡政紀の発話機能論
5.4.1 発話役割と連
5.4.2 語用論的条件と命題内容条件
5.4.3 語用論的条件の共有
5.4.4 ≪付与≫からの連の開始
5.4.5 会話における≪要求≫と≪付与≫の諸相
5.4.6 発話機能の5分類
5.5 発話機能の各範疇
第6章 ポライトネス理論
6.1 リーチのポライトネスの原理
6.1.1 気配りの原則・寛大性の原則
6.1.2 是認の原則・謙遜の原則
6.1.3 一致の原則
6.1.4 共感の原則
6.2 B&Lのポライトネス理論
6.2.1 フェイスとFTA
6.2.2 ポライトネス・ストラテジー
6.2.3 ポジティブポライトネス・ストラテジー
6.2.4 ネガティブポライトネス・ストラテジー
6.2.5 ほのめかしのストラテジー
6.3 ポライトネス理論のまとめ
第7章 日本語の配慮表現
7.1 配慮表現とは何か
7.2 配慮表現研究史
7.2.1 日本におけるポライトネス理論の紹介
7.2.2 国語審議会・井出祥子の「敬意表現」
7.2.3 配慮表現研究の展開
7.3 配慮表現における慣習化と定義
7.3.1 慣習化と原義の喪失
7.3.2 日本語配慮表現の事例?「ちょっと」
7.3.3 日本語配慮表現の事例?「かもしれない」
7.3.4 配慮表現の定義
7.3.5 メタファーとのアナロジーと辞書への登載
7.4 配慮表現の原理
7.5 配慮表現の分類
7.5.1 形式分類
7.5.2 機能分類
7.6 配慮表現の語彙の記述例
あとがき
参考文献
索引
山岡 政紀[ヤマオカ マサキ]
著・文・その他
牧原 功[マキハラ ツトム]
著・文・その他
小野 正樹[オノ マサキ]
著・文・その他
目次
序章 本書を始めるに当たって
第1章 語用論の基礎
第2章 協調の原理
第3章 関連性理論
第4章 発話行為論
第5章 発話機能論
第6章 ポライトネス理論
第7章 日本語の配慮表現
著者等紹介
山岡政紀[ヤマオカマサキ]
1962年、京都府生まれ。筑波大学第一学群人文学類卒業。筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科単位取得。現在、創価大学文学部人間学科教授。博士(言語学)
牧原功[マキハラツトム]
1963年、茨城県生まれ。筑波大学第二学群日本語日本文化学類卒業。筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科単位取得。現在、群馬大学国際教育・研究センター准教授
小野正樹[オノマサキ]
1965年、愛知県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科単位取得。現在、筑波大学大学院人文社会科学研究科教授。博士(言語学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。