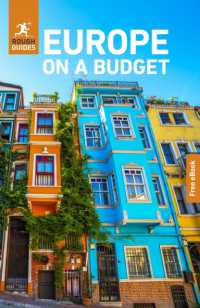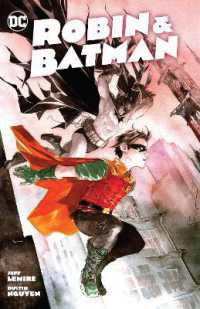内容説明
急激にボーダレス化する国際社会時代を眼前にして、日本語教育は今、その座標軸を転換する。本書では、これからの日本語教育を駆動する新しい理念とその実践を“言語習得・年少者教育・言語文化教育”という3領域を中心に、早稲田大学大学院日本語教育研究科からお届けする。新時代の日本語教育が、ここに。
目次
第1部 新時代の日本語教育をめざして―早稲田から世界へ発信
第2部 早稲田大学大学院日本語教育研究科の取り組み(言語習得研究の新たな転換;新しい習得研究の流れ;年少者日本語教育学の研究主題と方法 ほか)
第3部 大学と社会を結ぶ実践研究活動(産学官連携プロジェクトと日本語教育実践研究;新宿区の「早稲田モデル」実践;言語文化教育研究室とNPO法人「言語文化教育研究所」)
第4部 文献紹介(言語習得;年少者日本語教育;言語文化教育)
著者等紹介
宮崎里司[ミヤザキサトシ]
早稲田大学大学院日本語教育研究科教授。モナシュ大学日本研究科博士課程修了。応用言語学博士(Ph.D)。早稲田大学オーストラリア研究所所長、モナシュ大学及び早稲田大学日本語研究教育センターを経て現職。専門は、第二言語習得、オーストラリアの言語教育政策。墨田区での産学官連携プロジェクトや、テレビ会議システム・オンデマンドを利用した遠隔日本語教育に携わりながら、日本語教師による社会との響きあい、そして「軸足」固めの重要性を説く。2004‐2005年プリンスト大学、モナシュ大学、オックスフオード大学客員研究員
川上郁雄[カワカミイクオ]
早稲田大学大学院日本語教育研究科教授。大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。専門は、日本語教育、文化人類学。1990年より1992年までオーストラリア・クイーンズランド州教育省日本語教育アドバイザー(国際交流基金派遣日本語教育専門家)。1993年、宮城教育大学の日本語教育担当教官(助教授)として赴任、宮城教育大学教授を経て、2002年、早稲田大学日本語研究教育センター教授に着任。2003年より現職。平成13年(2001年)より文部科学省の「学校教育におけるJSLカリキュラムの開発に係る協力者会議」の委員を務める
細川英雄[ホソカワヒデオ]
早稲田大学大学院日本語教育研究科教授。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(教育学)。信州大学・金沢大学を経て、現職。NPO法人「言語文化教育研究所」代表。フランス国立東洋言語文化研究所日本語講師(1983‐84)、パリ大学交換研究員(1995‐96)。2001年4月の日本語教育研究科開設に際し、教務担当として参画。2004年9月より同研究科長を務める。専門は、言語文化教育論。母語としての国語教育と第二言語としての日本語教育の接点を模索しつつ、ことば・文化・社会を結ぶ第三の言語教育をめざし、その言語学習都市空間の設計デザインと実施プランの作成を提案する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。