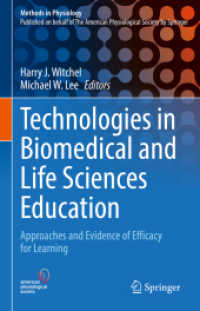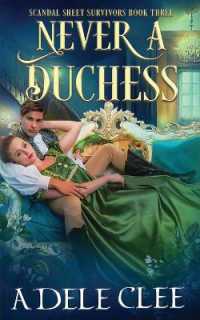出版社内容情報
現在の管子76篇は、春秋時代斉の名宰相管仲とその門人たちの編といわれ、名言・佳句に富み、その主唱する法冶主義に立った政治哲学・経済政策など、異彩を放つ卓見が随所に見られる。わが国には平安初期に伝えられ、韓非子と並ぶ法家思想の聖典として、経綸の要典として重んじられ、江戸時代には注釈も多く行われたが、中でも安井息軒の業績は有名である。今日の政治・産業や教育に対しても示唆に富み、本書による新訳には大きな期待が寄せられている。
目次
■第18巻
入国第五十四(襍篇五)
九守第五十五(襍篇六)
桓公問第五十六(襍篇七)
度地第五十七(襍篇八)
■第19巻
地員第五十八(襍篇九)
弟子職第五十九(襍篇十)
言昭第六十(襍篇十一)〈亡〉
修身第六十一(襍篇十二)〈亡〉
問覇第六十二(襍篇十三)〈亡〉
牧民解第六十三(管子解一)〈亡〉
■第20巻
形勢解第六十四(管子解二)
■第21巻
立政九敗解第六十五(管子解三)
版法解第六十六(管子解四)
明法解第六十七(管子解五)
臣(匡)乗馬第六十八(軽重一)
乗馬数第六十九(軽重二)
問乗馬第七十(軽重三)〈亡〉
■第22巻
事語第七十一(軽重四)
海王第七十二(軽重五)
国蓄第七十三(軽重六)
山国軌第七十四(軽重七)
山権数第七十五(軽重八)
山至数第七十六(軽重九)
■第23巻
地数第七十七(軽重十)
揆度第七十八(軽重十一)
国准第七十九(軽重十二)
軽重申第八十(軽重十三)
■第24巻
軽重乙第八十一(軽重十四)
軽重丙第八十二(軽重十五)〈亡〉
軽重丁第八十三(軽重十六)
軽重戊第八十四(軽重十七)
軽重己第八十五(軽重十八)
軽重庚第八十六(軽重十九)〈亡〉