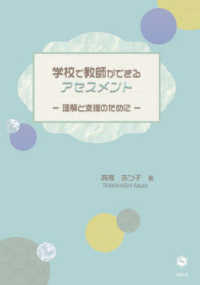- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
宮本 常一[ミヤモト ツネイチ]
著・文・その他
香月 洋一郎[カツキ ヨウイチロウ]
編集
毛利 甚八[モウリ ジンパチ]
解説
内容説明
牧野・石橋・井堰・棚田・焼畑・杉山…ひろがる自然に刻まれた人間の営為。暮らしの持続と向上につとめ世代をついできた人びとのたゆまぬ意志と人生をよむ九州脊梁山地の旅。
目次
合志義塾の周辺
肥後の石橋
阿蘇の牧場
ボタ山地帯をゆく
阿蘇にのぼる
球磨
五木・五家荘
矢部・入佐
馬見原
蘇陽峡
阿蘇高森から小国へ
初冬の阿蘇
久留米から日田へ
由布から阿蘇まで
阿蘇から日田へ
日田・英彦山
米良・椎葉の旅
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
31
課題はあるけど嘆く必要はない、前を向いて活動してる人々に注目せよ。そう言われてるように感じる。◇英彦山から阿蘇・矢部・五木と九州中央を縦断して椎葉・米良まで。この村々、以前仕事でレンタカーのカローラ走らせ何度も回った。出てくる地名に交差点のコンビニが思い浮かぶ(笑)。地の人にも移住してきた人にも話を聞いて夜はスナックに混ぜてもらって。職場の人皆に大変がられてたけど、楽しくて仕方なかった。◇農家の塾、牧草地改善、杉の植林、宮本が歩いてからは数十年たってたけれど、人々の丁寧な暮らしぶりは何ほども変わってない。2016/09/29
KAZOO
20
阿蘇は何度か行った事がありますがここに書かれているようなことからは想像もできないくらいの観光地化していました。球磨・人吉は行った事がなくこのようなものかと受け入れていますが、今はやはりかなり変わっているのでしょう。昭和の前半の時代の様子ですが日本人というのは農業や植林にしても本質は努力型の性格なのでしょうね。2014/09/08
HANA
5
いままで読んだ二冊(京都・青梅)よりも宮本常一らしさが出ていたように思う。全編にわたって農地の貧しさと農民の苦悩、それでも何とか生産を上げようとする闘いが描かれている。それらの中でも合志義塾や放牧、植林といった試みが興味深く読めた。2010/10/22
-
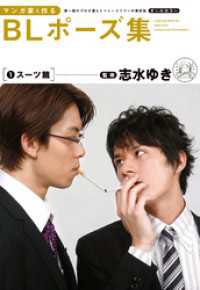
- 電子書籍
- マンガ家と作るBLポーズ集(1) スー…